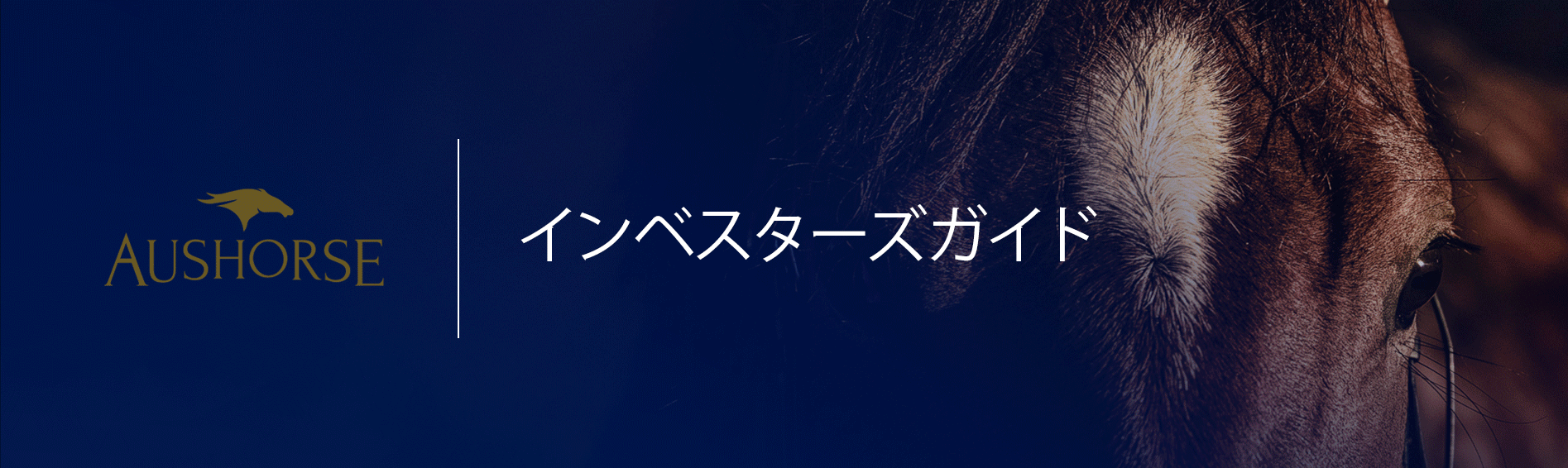勇気ある男というのは、内なる声もさらけ出せる。ジョー・プライド調教師を“秘密主義”だと非難する人間はいないだろう。しかし、彼の真の物語は、その袖の下に隠されている。
オーストラリアで調教師として表舞台に現れるとき、プライドはスーツと長袖のシャツを着て正装をしているため、それを目にする機会は滅多にない。
しかし、シドニー南西部のワーウィックファーム競馬場に構える厩舎では違う。蒸し暑い、初夏の朝。ジョーの腕の内側には、確かに喜びと“プライド”の証が刻まれていた。
『ステップスインタイム』
記憶力の良い方なら、きっとこの名前に聞き覚えがあるはずだ。ステップスインタイムは、シドニーで10年以上前に走っていた牝馬の名だ。
ジョン・オシェイ調教師がゴドルフィン・オーストラリアの主任調教師に就任する前、ステップスインタイムは彼の厩舎で走っていた。その後、プライド師のもとに転厩すると、移籍2戦目で待望のG1初制覇を挙げ、彼の厩舎でキャリアを終えた。
そうして彼は、タトゥーパーラーの扉をくぐった。刺青は派手なものではない。ただのブロック体の文字だ。
そして、同じような名前がほかにも刻まれている。レッドオッグ、ヴィジョンアンドパワー、セイクリッドチョイス、タイガーティーズ、エドゥアルド。自身にとって特別な意味を持つ愛馬たちの名が、その体に刻まれている。その隣には、より精巧なイラストも彫られている。彼がこよなく愛する、ナショナル・ラグビー・リーグ(NRL)のサウスシドニー・ラビトーズがモチーフのデザインだ。
プライドは肩をすくめる。「タトゥーっていうのは面白いものですよ」と。「最初、レッドオッグのやつを入れたときは、『やっちゃったな』となりました。でもその後も入れ続けた。ほとんどは見えない場所に彫っています。でも、それだけの馬なんです。プライヴェートアイはまだですし、チェオルウルフが最後になるかもしれませんね」
プライド本人、そして彼の10代の息子、ブレイヴと一緒に過ごせば、ほどなくして気づく。競馬に縁が無い家庭に生まれ、学生時代は心理学を学び、後にジョン・サイズ調教師のもとで修行した彼は、競馬の世界で最も面白い人物のひとりだということに。その控えめなタトゥーも含めて、だ。
彼のキャリアは、トップに向けて順調な軌道を描いてきたように見える。そしてその頂点がスプリングカーニバル、チェオルウルフが総賞金500万豪ドル(約5億円)のキングチャールズ3世ステークスを連覇し、国内屈指の名馬に名を刻んだあの瞬間だった。
チェオルウルフの近1年は成績にムラがあったが、最大の試練の日に、プライドはこのセン馬にブリンカーを着けた。競馬ファンの間では、プライド厩舎の馬がブリンカーを着ける時ほど効く「馬具の変更」はない、という冗談がよく言われる。
プライドは「ちょっとしたコツはありますけど、もちろん社外秘ですよ」と笑う。「ブリンカーは自分にとって素晴らしい馬具ですし、外から見て観察してみれば、どういうことか解き明かせると思いますよ」
秘伝のソース、そのレシピの全ては明かさない。しかし、Idol Horseとの約1時間に及ぶインタビューの中で、プライドは、自分と馬がどういうメカニズムで動いているのかをしっかり理解する手がかりを与えてくれる。
そうして彼は、オーストラリア競馬に押し寄せた巨大厩舎の波とも十分に渡り合えるのだ。トップ厩舎が何百頭と管理馬を引き受けるとの比べて、プライド厩舎の方針は常時70頭規模を貫いている。
パウンド・フォー・パウンド(階級差無しの最強議論)で見た時、彼はオーストラリア最高の調教師なのか。
「そう言われるのは好きだね」とプライドは微笑む。「一流の選手を比べるのはすごく簡単。ですが調教師はどうなのか?ほとんど無理な話ですよね。仮に同じ10頭を与えたら、そこに何か答えが出るかもしれないですけども」
「たとえば、ゴドルフィンが専属調教師制度から方針転換して、各厩舎の調教師たちに馬を分散させるようになりましたが、現時点では、ゴドルフィンの馬で一番勝っているのはうちです。競馬で“同じ条件”を作るとしたらそれくらいでしょうか」
「それ以外で、比較する方法がありますかね?」
サイズ師の弟子であるプライドは、朝の運動後に馬に与える飼い葉を1日1回と決めている。多くの調教師は、日中と夜に少量ずつ2回、飼い桶を満たす。彼は週3回という標準的な追い切り回数より少なくし、走らせる距離も短い。脚に“キレ”を残しておきたいのだ。プールは、ほとんどの調教師にとって巨大で、十分に活用されていない資産だ、と彼は考えている。
データと分析。頭ごなしに否定はしないが、ほとんど使っていないとも言うことを恐れない。オーストラリア東海岸のあちこちに馬を配置する他厩舎の軍拡競争とは違い、プライドはすべてをワーウィックファームに置く。
だから、見たい時にいくらでも見られるし、見ないときは任せるという選択も自由にできる。
「大きな厩舎にケチをつけたいわけではありませんが、うちにアドバンテージがあるとすれば、馬を分析するという点でうちに強みがあります。馬があちこちの厩舎に散らばっている調教師とは違いますからね」とプライドは言う。
「全部が同じ屋根の下にいる。これはアドバンテージだと思う。アドバンテージでしょう」
「調教師のマーク・カヴァナーが昔こう言いました。『調教とは、相馬眼の科学だ』と。自分はそれを強く信じています。観察して、見えたことを追いかけていく。追い切りが必要だと思えば、追い切る。データが必要ないと言ったらどうします?追い切らない?」
「追い切りが良くなかったのに、データが良いと言っていたとしても、自分は追い切りが良かったとは思いません。大抵、自分の直感はこういう場合当たっている。そこにデータが必要だとは思えない。見たものを信じたいんです」

彼の名前は腕にも刻まれていないが、1980年代に現役時代を過ごしたペリスコープというベテランホースが、ジョー・プライド調教師の未来を描くうえで最も重要な馬だったのかもしれない。
プライドはある水曜日、高校をサボって、仲間たちとカンタベリー競馬場に忍び込んだ。昔の平日開催は、現代のように競馬ファンとオンラインブックメーカーがネット上で取引する幽霊のような日々とは違い、はるかに多くの人が現地に来ていた。
プライドは10豪ドルを握りしめ、競馬場に参戦した。最終レース、ペリスコープの単勝オッズは101倍。複勝は26倍だった。プライドは複勝の方に2豪ドルを賭けた。結果、ペリスコープはどうにか3着以内に滑り込んだ。
「で、ハマったんだ」と彼は言う。
プライドの幼少期は、大抵“必死なギャンブラー”たちの周りで過ぎていった。家族は遠くへ、そして頻繁に引っ越した。オーストラリアの首都、キャンベラのすぐ外にあるクイーンビアンで生まれたプライドは、成長の重要な時期の多くを、ニュージーランドのダニーデンで過ごした。
父はさまざまな分野で仕事を得られたが、主に配管工や排水工だった。「父は、これまで住んだ家の数と同じくらい仕事を転々としていましたよ」とプライドは言う。
やがて一家はオーストラリアとシドニーに戻り、西部の郊外を転々とした。その一部は市の東部より社会経済的に厳しい地域でもある。プライドが自分を「ウェスティー(西部生まれ)」と呼ぶが、それは誇りのバッジのようなものだ。おそらく彼の知性を隠すための表向きの顔でもあるのだろう。
シドニーの大学で学士課程に入学したプライドは、心理学の分野で一発当てれば収入には困らないだろう、という小さな野心を抱いていた。だがすぐに、人間の心理学にほとんど興味がないことにも、早く金持ちになることにも大して興味がないことにも気づいた。
サラブレッド業界に家族のつながりはなかったが、ヴィンテージクロップがメルボルンカップを勝った1993年、彼は金を稼ごうといくつかの厩舎の門を叩いた。競馬の魔法に引き寄せられて。
「ワクワクするスポーツでしょ?」とプライドは言う。「それに動物っていう存在が、一緒に仕事をする上でやりがいのある相棒だと気付いた瞬間、もうそれで決まりでした。当時の90年代は、ワクワクする仕事が少なかったんです。でもこれは不思議な魅力があった」
「どっぷり浸かってしまって今では、その感覚はなくなったけど、当時は本当に不思議な魅力がありました。良い馬に夢中だったし、あの時代は良い馬がたくさんいた」
「記憶が美化されているだけかもしれないけど、競馬にあれ以上の時代があったとは思えないです。昔ながらの魅力と、テレビ中継されるくらいには現代的な要素、この二つが絶妙な混ざり方をしていました」
ローズヒルで競馬界に足を踏み入れたプライドは、敏腕トレーナーのバリー・ロックウッド調教師とブルース・ジョンソン調教師のもとで働き、次にロイヤルランドウィックへ移り、ビル・ミッチェル調教師から学んだ。
だが、サイズ師ほど彼に影響を与えた人物はいない。サイズはその後、香港競馬で王朝を築くことになる。
「明らかに世界最高のトップトレーナーです」とプライドは称賛する。「それに異論を唱えられる人はいないと思う。その下で働けたのは本当に大きかったです」
サイズは決して社交的なタイプではなく、毎日会っている人間にとっても、彼は無口な存在だった。プライドは彼の後をついて回り、ただ見て、待って、口から何か、どんなことでも出てくるのを聞こうとした。
サイズの厩舎には、すでに別の調教師で試行錯誤され、(時に非現実的な)オーナーの期待に届かなかった新入りの馬が、当時としてはずいぶん頻繁に入ってきた。あの頃は、馬が頻繁に厩舎を替える時代ではなかった。オーナーには担当調教師がいて、基本的にはそのまま付き合い続けた。
だがサイズは、成績が上がらないベテラン馬を何頭か引き受けると、それを突然勝たせ始めた。それを側で見ていたプライドは不思議でならなかった。
「あんなに馬を再生できるのは信じられないほどでした。自分のお気に入りはキッドマンズコーヴです。最初は良い馬だったのに徐々に迷走して、最終的にジョン(サイズ師)が引き取って立て直した。たった数ヶ月のうちに、タイザノットとジェネラルレディムを倒す馬になったんです」
「彼は一度だけではなく、それを何度もやった。入ってきた馬を見て、『これは動かないだろう』と思っても、案の定、彼は動かした。馬を分かっている人なんですよね」
プライドがサイズの側近として過ごしたのは4年だけだった。ある日、ほとんど予告もなく、サイズは香港ジョッキークラブ(HKJC)からの移籍オファーを受けると言い、香港競馬へと去っていった。
「馬を何頭か、オーナーも何人か渡す。あとは幸運を祈るよ」とサイズは彼に言った。
プライドは当時のことを振り返り、このように言う。
「話はしたけど、彼はあまり答えをくれなかった。すごく端的で、要点だけ……逆にそれが良いことなのかもしれないです。自分で見て学んで、考えて答えを出さなきゃいけなかった。何をすべきか情報を教科書通りに与えてくれる人ではなかった。だからこそ、いなくなるのが怖かった」
「あの数年間は恐る恐るの日々でした。よく『俺はやらかしたのか?』と考えていました。金銭トラブルってほどじゃないけど、懐事情は苦しかった。週の給料を払う金はあった。でも何かが起きたら、支えも命綱もまったくなかった。乗り切ったけど、もう一度やりたいとは思えないですね」
ある種の当然かもしれないが、プライドの評判は師匠とよく似ている。ほかで伸び悩んだ馬を立て直す、競馬界の再生工場だ。
輸入馬にはほとんど手を出さず、過熱するオーストラリアの1歳馬市場で高い馬を仕入れることもない。その代わり、地元生まれのタフな騸馬を主軸に据え、シーズンを通して何年も走れる厩舎ラインナップを作り上げている。
プライドは調教師として、自分には無理だと思う馬にまだ出会っていない。
「難しい馬というパズルと向き合って、どうやってベストを引き出すかという謎解きに惹かれるんです」とプライドは言う。
「難しいパズルこそ、解きたいんです」
「人間は複雑すぎて自分には解けませんよ。自分は単純な人間だし、馬は嘘をつかないのが好きなんです。馬はどこまで行っても馬でしかない。こちらがやることに応えて、その効果が見える。ベストを引き出せたら、あとは本当に楽しい」
「チェオルウルフなんかは、ようやく解明できたところです。良い馬だとは分かっていました。最初の2つのG1を勝って、そのあと12か月は低迷した。キングチャールズを勝てて、自分としては本当にホッとしました。頭の中では、もう謎は解けたと思っていて、そこから先はどこまで行けるか楽しむだけです」
自身の腕への自信は、SNSにも表れている。かつてのプライドは、自分の馬を猛烈に擁護し、ランカンルピー、シャトークア、ネイチャーストリップのような名馬にも勝てる馬がうちの厩舎にはいる、と豪語していた。
勝つ時もあれば、勝てない時もある。勝てなかった時こそ、彼はあらゆる声を聞くことになった。
50代に入って時が経ったせいか、今のプライドはX(旧Twitter)で煽り立てる頻度はそこまで多くはない。チェオルウルフ、プライヴェートアイ、そしてゴドルフィンのG1馬・アティカといった逸材が厩舎が潤している今現在の好調ぶりを思えば、昔のようならと思わざるを得ない。
プライドは、豪州で最も賞金の高いレース、総賞金2000万豪ドル(約20億円)のジ・エベレストも制している。シンクアバウトイットだ。胸前の薄い、細身の騸馬で、破竹の9連勝で一気に頂点へ駆け上がると、ほとんど同じくらいの勢いで姿を消した。
「逆風だらけだったけど、この馬と過ごせた12か月は最大限に活かせました。その後、彼は燃え尽きたように終わってしまいました」とプライドは言う。「だから、ああいう馬を見て『こうすべきだった、ああすべきだった』とは思いません。ある意味、うちはやりすぎたくらいの結果を出したと思っています」
それでも、“もっとやれた”と思う馬が1頭いる。G1を2勝した快速馬、テラヴィスタだ。
「あの馬は特殊でした。本当に……自分では……。彼に何が起きていたのか、最後の方には分かった気がします。最初に勝っていた頃、走るたびに熱中症を起こして、よろめきながら戻ってきました。きっと燃え尽きてしまったんだと思います」
「テラヴィスタは『もしも』を思わせる馬でした。今の自分がこの馬を託されたとしても、何を変えたか分からない。馬が厩舎を去って、ベストを引き出せなかったと思う時ほど、嫌な気持ちはありません」


プライドが手掛けてきた名馬たちの写真が掲げられた、仮設の厩舎事務所に座っていると、こんなに若い人間が、これほどの知恵を語ることができるのかと驚くような一幕があった。
トレーナーの息子、ブレイヴ・プライドはまだ19歳だが、すでに父の厩舎で働いている。その話し方は、まるで何十年も業界にいるベテランのようだ。ジョーはブレイヴにも、2人の娘にも、自分の後を継がせようと無理強いしたことはない。
だがこの6年間、ブレイヴがやりたいことは土曜日に競馬場へ行くこと、それだけだった。学校のスポーツは邪魔になり始めたので辞めたという。
「趣味は競馬なんです」とブレイヴは言う。
「ほかのことをやる考えはありませんでした。私も姉たちも、『競馬を好きになれ』というプレッシャーは一切ありませんでした。競馬が身近だっただけです。6年前の土曜に競馬場へ行く時に感じた気持ちは、今も変わりません。家で仕事するより、金曜も競馬場に居たいんです」
ブレイヴは、厩舎の現役、そして過去のスターたちの実績を次々と挙げていく。チェオルウルフのような主役級のG1馬だけでなく、条件戦でコツコツ稼ぐような馬も同じくらい愛する存在だ。
10月のキングチャールズ3世ステークス当日、ブレイヴは前のレースでコールクラッシャーの馬装をして、シドニーステークスの後に厩舎へ連れ帰った。チェオルウルフの出番まで間もない頃、自分が緊張しすぎて家まで運転できないことに気づいた。だから車の中で携帯電話でレースを見た。
「叫んで窓を叩いてました」とブレイヴは笑う。「誇りっていうのもあるし、あいつは本当に真面目な馬なんです。自分に疑いが出てきたり、周りから『大した馬じゃない』って言われたりする。自分を信じて、やるべきことをやって結果を出す。それ以上に特別なものはないですよ」
ジョーはすぐにブレイヴを共同調教師に加える予定はないし、自分が双眼鏡を置く日が来た時にどうなるかを描いているわけでもない。以前に海外で新たな挑戦を始めるチャンスもあったが、今は興味がない。
「調教師が引退しても、ビジネスを売ることはできません」と彼は言う。「あるのは信頼だけだ。道具と信頼です。まだ道半ばですが、やりたかったことの多くは達成してきた。競馬の世界では素晴らしい経験を味わってきました」
「もし引退して、そこでプライド・レーシングが終わっても構いませんが、息子や娘の誰かが引き継ぐっていうのも魅力があります。ただ、彼らがやりたいことの犠牲には絶対にしたくない。自発的に、自然な流れで進んでいってほしいですね」
すでにブレイヴは、その“持ち前の資質”を証明している。それどころか、単なる親譲り以上かもしれない。彼は堂々と、自分の好きな馬はコールクラッシャーだと挙げる。父が調教した中でベストの馬ではないことは分かっている。それでも一番好きだ。
そして、その理由を熱っぽく語り終えるやいなや、彼はシャツの左側を少し引き下げて、胸に刻まれたものを見せた。コールクラッシャーがモデルのタトゥーだ。
最高の師匠から学んだスタイルが、そこにはあった。