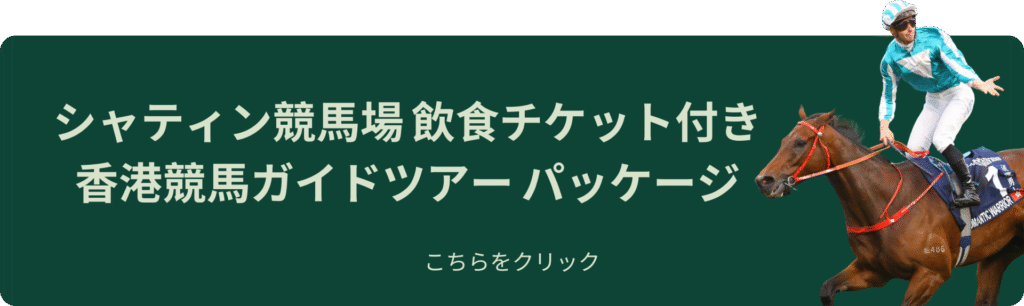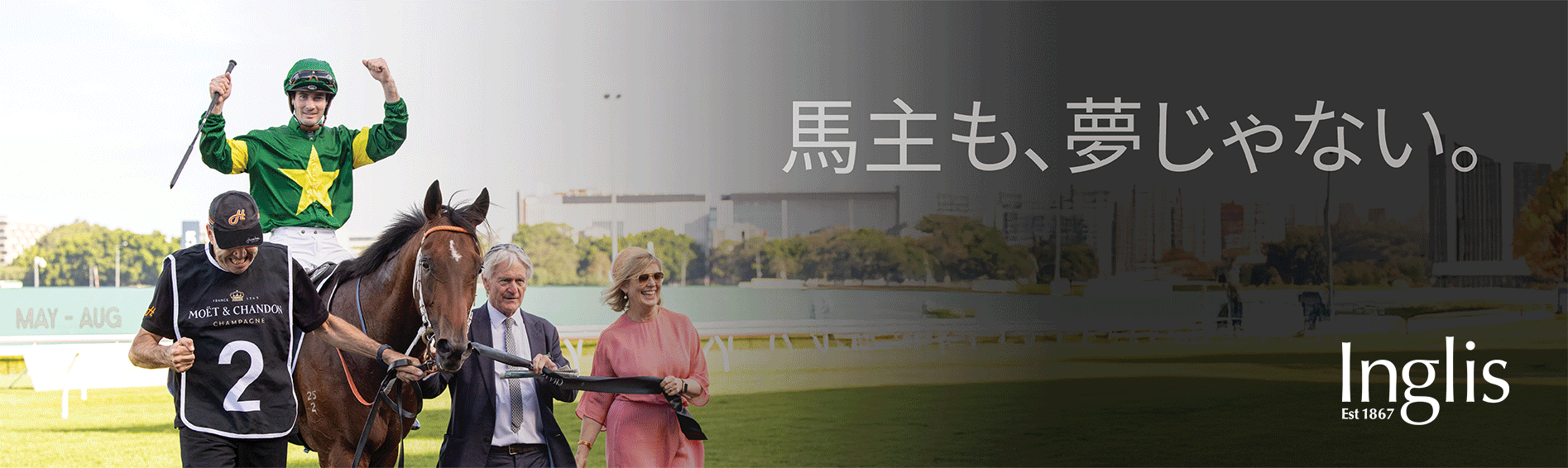ミカエル・バルザローナ騎手がゴール後に手を伸ばし、クリストフ・ルメール騎手と握手した時、それは単なるスポーツマンシップの一幕を超えた、象徴的な光景に思えた。
日本が世界に誇るG1レースで、フランス人騎手によるワンツーフィニッシュ。かつてアガ・カーン殿下の主戦として緑の勝負服をまとった46歳のルメール騎手に、34歳のバルザローナ騎手がアタマ差で競り勝った。その握手は、世代と東西をひとつに結びつけるようなものだった。
バルザローナはカランダガンに騎乗し、ジャパンカップを制した。ルメールはマスカレードボールに騎乗し、アタマ差まで迫っていた。
ルメールがかつてアガ・カーン殿下の主戦の座を外されたことが、彼を日本という予期せぬ道へと導いたのだとすれば、今回バルザローナがアガ・カーン殿下のカランダガンで勝利したことで、ひとつの物語がひとまず完結したかのようにも見えた。
しかし、このカランダガンの勝利には、それ以上に大きな意味があった。ジャパンカップが国際的なイベントとして命脈をつなぐうえで、分岐点となる一戦だったのかもしれない。
競馬では、ほんのわずかな差が、まったく異なる現実を生み出すことがある。もし着差が逆だったら、今日の話題はずいぶん暗いものになっていただろう。
またもや外国馬が敗れたという事実。欧州の陣営が遠征を見送る理由がさらに一つ増えたという話。そして、日本の水準を引き上げる目的で1981年に創設されたこのレースが、今や外からはほとんど勝てないレースになってしまったという、あらためて突きつけられる現実だ。
数字はそれを物語っている。2005年のアルカセット以降、外国からは60頭の遠征馬が出走したが、勝利は一度もなかった。そのうち、2006年には欧州年度代表馬のウィジャボードが3着に入ったものの、それ以降、外国馬は一度も3着以内に入っていない。
62頭中、46頭が8着以下に沈んでいたのだ。この10年ほどで国際色はさらに薄れ、コロナ禍の影響だけでなく、堅い馬場への懸念や、さらに手強くなった日本勢への恐れから、出走頭数は減少していった。
たとえ高額なボーナスが用意されても、調教師たちは“地球の裏側”までトップホースを送り込んで敗れることに、メリットを見いだせなくなっていた。
だからこそ、この勝利は重要だった。欧州でG1を3連勝し、世界のトップクラスの芝馬と評価されていたカランダガンが勝てないのだとしたら、一体どんな馬なら勝てるというのか。ここでまた敗れていたら、海外からの挑戦の流れは完全に途絶えていたかもしれない。
その代わりに、今回は勝てるということを証明してみせた。しかも、決して手薄な相手ではなかった。実績を並べれば明らかだ。アタマ差で敗れたのは天皇賞秋覇者のマスカレードボール、3着はドバイシーマクラシックでカランダガンを破ったダノンデサイルが入り、4着には日本ダービー馬のクロワデュノールが続いた。


これは正真正銘、世界レベルの一戦だった。そして決着は、アーモンドアイの2分20秒6を上回る、2分20秒3というジャパンカップ史上最速の走破タイムだった。
この王者から王者への“バトンリレー”だけが、ファンの感慨深い思いに繋がっているわけではない。
アガ・カーン4世(カリム・アル・フセイニ王子)殿下は2月に逝去しており、ザラ王女は今年について「ここ長い間の中で最高の年だと感じている」と認める一方で、不在と記憶に満ちた一年でもあったと語っていた。
王女はカランダガンについて「良い馬、成長著しい馬」と話し、フランシス=アンリ・グラファール調教師が「最高の場所へ、最良の日に、最適なタイミングでカランダガンを日本へ連れてきてくれた」と称えた。
振り返ると、彼らはジャパンカップを手にしたことがなかった。理由は明白、「この日のための馬がいなかった」からだ。だが今、相応しい馬が手元にいる。
新進気鋭のグラファール調教師は、2025年に入ってすでにG1を14勝し、フランス人調教師としての年間G1勝利数でアンドレ・ファーブル調教師の記録を上回った。海外遠征にも積極的であり、遠征向きの馬も持っている。「カランダガンは非常にバランスが取れていて、長く脚を使って加速し、そのスピードを持続できます」と調教師は語る。
「カランダガンは真のチャンピオンです」
バルザローナの「私はこのレースで一番強い馬に乗っていましたから」という言葉は、さらに率直だった。
ジャパンカップは2025年を迎えるにあたり、ある種の存在意義の危機に直面していた。依然として素晴らしいレースであり、今年も7万7,000人の観客を集め、日本競馬が若い世代のファンの増加による人気急上昇に沸くなかで、発売金額は260億0814万3100円(約1億6,670万米ドル)という桁違いの数字に達していた。
それでも、日本が世界に誇る看板レースであるジャパンカップは、年を追うごとに国内色を強めていた。
そこへ、カランダガンがサンクルー大賞、キングジョージ、英チャンピオンステークスという、ヨーロッパのG1・3連勝で勢いに乗ってやって来た。世界王者が、日本のトップホースたちと戦うべく、アウェイに乗り込んでくる。まさにこのレースが本来そうあるべき姿の通りだった。
もし彼が負けていれば、何も変わらなかったかもしれない。しかし、カランダガンがレコードタイムで、天皇賞馬、ダービー馬、そしてドバイで自分を破った馬を相手に勝ってみせたことで、ジャパンカップは再び「外国馬が狙うに値するレース」として存在感を取り戻した。
今、話題はまったく違うものになっている。日本のフォーエバーヤングがBCクラシックを制し、フランスの馬がジャパンカップを制した。競馬というスポーツが発展するために切実に必要としている東西交流のサイクルは、新たな生命を吹き込まれ、再び双方向に流れ始めた。
ザラ王女は、再びの参戦の可能性さえほのめかしている。
「適切な馬が、適切な日に、適切なコースであれば、私たちは遠征します。可能であれば、おそらくそうするでしょう」
ジャパンカップは、まさにこのような結果を必要としていた。そしてその結果は、わずかアタマ差で実現した。