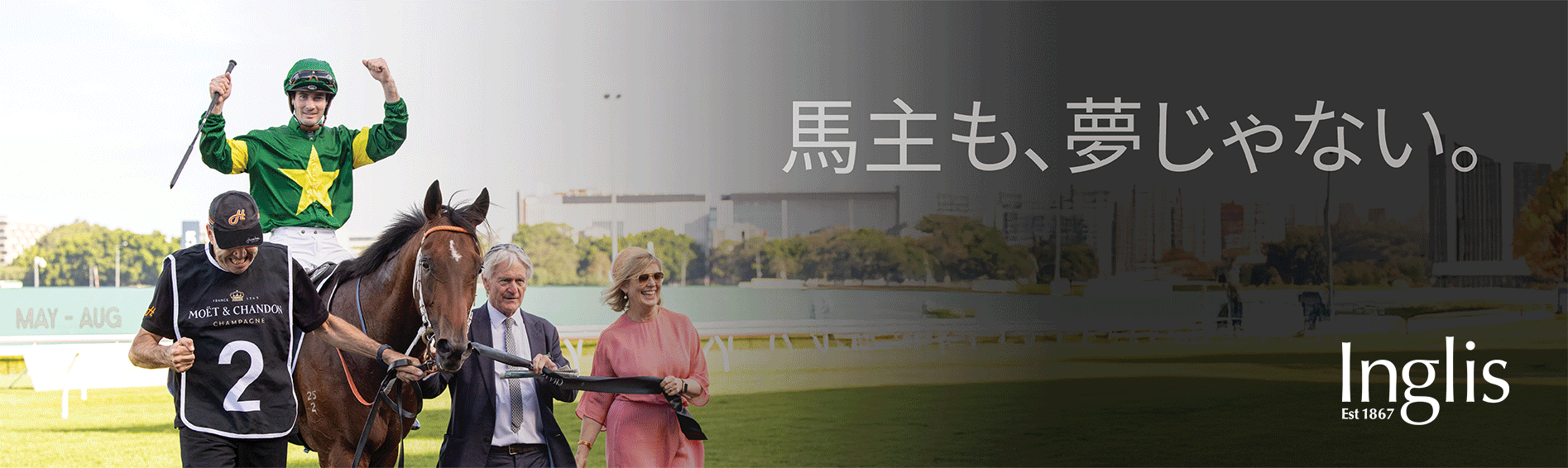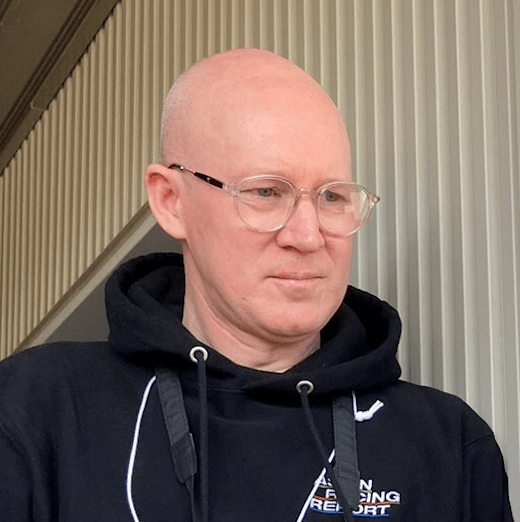アスコット競馬場は先週、2024年の決算報告で過去最高の収益を発表した。夏の大一番であるG1・キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス、そして国際的な存在感の強化につながりそうだ。
キングジョージは欧州夏競馬の頂点であり続けているとはいえ、ここ数年でかつての高みに比べ、やや輝きを失っている。10月のパリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞が、かつては互角とされた存在から、事実上の欧州王者決定戦にのし上がったからだ。秋のブローニュの森が、夏のバークシャーを凌駕している。
その差の要因は、賞金の規模に加え、凱旋門賞が日本調教馬を毎年のように呼び寄せる力にある。今年のキングジョージも、欧州トップクラスのカランダガン、ヤンブリューゲル、レベルズロマンス、カルパナ、そして英愛ダービー馬のランボーン(執筆時点では出走の可能性あり)らが、史上最高の総賞金150万ポンドを懸けて激突する見込みだ。しかし、グローバル化を牽引する『World Pool(ワールドプール)』時代に求められる国際的な広がりという点では物足りなさが否めない。
香港からアイヴァン・アラン調教師のインディジェナスが出走し、6着に終わった1999年以来、欧州以外で調教された馬はわずか7頭しかキングジョージに挑戦していない。内訳は南アフリカ1頭、アルゼンチン1頭、北米からハードバックが3着、そして日本馬が4頭だ。
日本馬の初出走は2000年のエアシャカール、最高成績は2006年のハーツクライの3着、直近は2019年のシュヴァルグランだ。アスコット競馬場は、日本の関係者を惹きつけるには、さらなる魅力的な誘因策が必要であることを理解している。
今回の発表には、税引前利益840万ポンドや、今年の賞金総額を過去最高の1775万ポンドに設定する賞金引き上げなど、好調を示す指標が並んだ。その中で語られたのは『世界的な存在感の向上』であり、それが今年の史上最高賞金の基盤になったと強調された。
この『世界的存在感』を高める一環として、キングジョージを本来あるべき地位へ押し戻すことが目標となる。そのためには、ロイヤルアスコットがすでに成功を収めているように、継続的に他大陸からの参戦、とりわけ日本のスターホースの招致が欠かせない。6月のロイヤルアスコットでのG1でサトノレーヴが2着に入ったことは、その取り組みを後押しする材料となるはずだ。
「今年のキングジョージに出走する日本馬はいませんが、私たちはこれからも働きかけを続け、賞金も引き上げていきます」とIdol Horseに語るのは、 アスコット競馬場のレース運営・広報ディレクター、ニック・スミス氏だ。
「日本では賞金が重視されます。キングジョージの賞金も強化する必要があります。150万ポンドは欧州基準では高額ですが、英国を代表する全世代中距離路線の頂点に立つレースとしては、もっと高くするべきで、実際そうなるでしょう」
「 日本では今もキングジョージや凱旋門賞を目標に、中距離馬を誇りを持って生産しています。私たちはその馬たちをキングジョージに呼びたいのです」
スミス氏はこれまでに ”25~30回ほど” 日本を訪れてきたというが、それは彼だけではない。英国やアイルランドのトップクラスの競馬場の幹部たちは、今世紀に入ってから毎年のように世界を飛び回り、非欧州調教馬の誘致に努めている。
グローバル化が進み、JRAとの海外レース同時発売や、香港ジョッキークラブが展開する高収益の『World Pool』が拡大を続ける今、それは『願望』から『必須』に変わりつつある。
「非常に密接に連携しています」とスミス氏は言う。「グッドウッド競馬場のエド・アーケルや、ヨーク競馬場のウィリアム・ダービーと一緒に動き、まさに一つのチームとして仕事をしています」
ヨーク競馬場のCEOであるダービー氏は、20年前の8月に同競馬場で日本の名馬、ゼンノロブロイが見せた走りを誇らしげに振り返る。そして今年8月、その記念すべき節目に合わせて、日本のダノンデサイルがヨーク競馬場で出走する可能性に大きな期待を寄せている。
「英国の3競馬場とレパーズタウンが協力するのは理にかなっています」とダービー氏は話す。
「国際的な馬は複数の目標を持つことが多く、我々が足並みを揃え一貫した対応をすることが、陣営にとっても理にかなっていますし、実際にうまくいっています」
ダービー氏はまた、2012年にヨークとグッドウッドで勝利した豪州の短距離女王、オルテンシアの走りにも興奮したと振り返るが、日本馬の魅力はさらに特別だという。日本競馬は世界でも屈指の健全さを誇り、JRAのG1競走の層の厚さは世界有数。条件さえ整えば、日本の一流馬は世界の舞台に姿を見せることになるだろう。
「日本との関係は非常に戦略的なもので、何年も前から取り組んできたものです」と、 レパーズタウン競馬場の暫定CEO、ヴィッキー・ドンロン氏は語る。実際には、アイルランドで日本調教馬が勝利したことはまだなく、G1・愛チャンピオンステークスに挑んだのも、2019年のディアドラと2024年のシンエンペラーだけである。
「日本の関係者、そして現地で協力している代理人や担当者との関係を築くには多くの時間と労力がかかり、しかもそれは信頼関係に基づいて成り立っているのです」
欧州、特に英国とアイルランドにとっての課題は賞金水準の低さだ。日本馬が狙う世界主要レース、特に高額賞金のドバイワールドカップ、サウジカップ、香港国際競走、ブリーダーズカップと比べれば見劣りする。キングジョージは英国で最も高額なレースのひとつだが、それでも150万ポンドはサウジカップの2000万米ドルには到底及ばない。
「春になると日本の馬が中東に集まって行くんです」とアスコットのスミス氏は語る。「私、ウィリアム(ダービー氏・ヨーク競馬場CEO)、エド(アーカル氏・グッドウッド競馬場レースディレクター)の3人は、自分たちの競馬場に1頭でも日本馬を呼べたら非常に嬉しいです」
今年初め、ロンシャン競馬場は凱旋門賞に向けてシーズンを通して出走馬を誘致する『優先出走権付きシリーズ』を発表した。またアスコット、ヨーク、グッドウッドは、7月から8月にかけて英国で複数の馬を出走させる陣営への奨励策として『ブリティッシュ・ミッドサマーボーナス』を導入。日本のG1馬の選択肢が限られる、6月中旬から8月下旬に合わせた戦略と考えられる。
「ヨーク、グッドウッド、アスコットの3競馬場の代表者が、長距離フライト中や空港ラウンジでの待機中に『どうすれば欧州や英国に夏の間、最高の馬を呼び込めるか?』と議論したのが始まりでした」とダービー氏は振り返る。
「この仕組みは、マイラー、2000m、2400mといった複数カテゴリーの馬を一緒に連れてきてもらうことを目的としています。サセックスステークス、キングジョージ、そして願わくばインターナショナルSまでつなげていければいいと思っています。きっと今年の経験から学ぶことは多いはずです」
ミッドサマーボーナスやフランスの出走奨励策は、アイルランド競馬にも刺激を与えたと、レパーズタウンのドンロン暫定CEOは語る。
「間違いなく競争のハードルを上げるものです」とドンロン氏。「私たちアイルランド競馬としても、将来どのように魅力を高めていくかを考えなければなりません」
そのためには、出走馬への輸送費補助が不可欠である。
アスコット競馬場のスミス氏はこれについて、「これはもう譲れない条件です。やらざるを得ないのです。今の世界では、輸送費補助は当たり前です」と語る。
アスコット競馬場では、おおむねレーティング115以上の馬に補助金が支払われ、その金額は移動距離やスター性によっても変わる。
「レーティング125超の馬、たとえばイクイノックスやウィンクスのような馬なら、まったく別のレベルの補助になります。特別な対応を用意することになるでしょう」とスミス氏は説明する。
「日本から来る馬はアメリカからの馬より補助額が大きくなります。これは輸送方法の違いによるもので、アメリカから来る馬の数は多く、競走馬輸送用の航空コンテナを複数馬で共有することが多いのに対し、日本からは1頭のみで利用する単独輸送となるケースがほとんどだからです」
この流れを後押ししているのが、英国・アイルランドではトート社が発売する『World Pool』だ。G1開催日に多額の売上をもたらし、今年のロイヤルアスコットでは15億8000万香港ドル(約2億5200万米ドル)の売上を記録した。
日本馬が出走した場合、日本中央競馬会(JRA)は政府の承認を得て、そのレースについて日本国内で馬券発売ができるようになる。これはWorld Poolとは別の仕組みであり、日本国内では独自のプールで発売される。
正確な数字は公表されていないが、競馬場はWorld Poolの分配収益として、1日あたり50万~60万ポンドを得ると広く報じられている。
「(売り上げは)現時点では少し低めでしょうね」と スミス氏は今年のロイヤルアスコット開催前にそう語っていた。実際には各日で前年比増を記録し、水曜日の総売上は3億3,070万香港ドル(約4,300万米ドル)という新記録を打ち立てた。
「立ち上げ期やコロナ禍の時期には、World Poolはかなり派手な数字を出しましたが、今はようやく安定期に入ってきたところです。まだ新しい仕組みで、非常に重要な収益源ですが、現時点で具体的な見通しを立てるのは困難です。それでも、数世代ぶりの賭けの仕組みの『イノベーション(革新)』であり、賞金について大きく貢献してくれていることは間違いありません」
競馬場は、日本でレースが同時発売された際のメディア権料収入も得ているが、その金額も公表されていない。
「日本馬が出走すればメディア権料収入という商業的メリットはありますが、想像されるほど大きな臨時収入や賞金の上乗せがあるわけではありません」とドンロン氏は話す。
「ただし、日本馬の出走はアジア全体の注目を集めます。日本からはWorld Poolに直接投票しませんが、日本馬を知っている香港など周辺地域では投票が増え、それが売上全体の押し上げにつながります」

World Poolの初開催は2019年6月のアスコット。スミス氏らはそれ以来、売上を左右する要因を注視してきた。
「実は、売上を動かしているのは馬よりもジョッキーなのです」とスミス氏は明かす。「欧州に来る国際的な馬の数はまだ多くないので、その構図を本格的に検証する機会はあまりないのですが、香港で関心を集めるジョッキーが誰かを見る方が興味深いことに気づきました」
その視点から、スミス氏はシャーガーカップのようなイベントでWorld Poolがどのような成果を上げるかに興味を示した。ただし、World PoolはG1と紐づく仕組みのため、実現の可能性は低いと付け加えた。
ドンロン氏は「商業的な視点で全てを見たくはない」と言いつつも、World Poolで馬券が売れ、その売り上げが大きければ、主催競馬場にもより多くの還元があるという現実を認めた。
「World Poolはすべて手数料制で、売上高に依存しています。だから誰もがその成功の利害関係者になります。つまり私たちもリスクを共有しているのです」と語り、欧州のワールドプール開催競馬場と香港ジョッキークラブ(HKJC)のWorld Poolチームとの定期会議で、経験やアイデアを共有していると付け加えた。
「World Pool対象レースの売上が増えれば、それだけ競馬場にとっても有益になります。売上を増やす要因はいくつかありますが、その中でも最大のものは出走頭数です。G1レースではこの点が難しく、理想の数字は8頭。8頭を下回ると売上は大きく落ち込みます」
国際馬の参戦は、もちろんその出走頭数を増やすことにつながる。
もっとも、World Poolや日本での同時発売が国際馬招致の要因となったのは最近のことで、2000年代初期の招致理由とは異なる。
スミス氏、ダービー氏、ドンロン氏はいずれも、国際馬を呼び込む主目的は常に「大レースのブランド価値を高め、競争の激しい国際市場で存在感を維持すること」にあると強調する。
「基本的にはブランドのためなのです」とスミス氏。「世界舞台での地位を得るために、アスコット競馬場は過去20年以上取り組んできました。リトルブリッジとブラックキャビアが同じ年のロイヤルアスコットで勝ったときのように素晴らしい年もありましたし、難しい年もありましたが、総じてうまくいっていますし、世界地図に名を刻むことができたと思っています」
スミス氏は、アスコット競馬場が『国際的視点』を本格的に取り入れ始めたのは、2004年の大規模改修に向けた数年間だったと振り返る。当時、馬場管理責任者を務めていたのはニック・チェイン氏。その前年、オーストラリア馬のショワジールがロイヤルアスコットでキングズスタンドSとゴールデンジュビリーSを連勝し、欧州勢を驚かせていた。
「欧州の枠を越えたのは初めてのことでした。当時は主に豪レーシング・ヴィクトリアとの提携を中心に、さまざまな競馬団体と連携を組み始めました。そこからすべてが始まったのです」
ちょうどその頃、ヨーク競馬場も国際化を加速させていた。ゼンノロブロイが2004年にジャパンカップと有馬記念を制し、名手武豊騎手に導かれてインターナショナルSで2着に健闘したのもその象徴だ。

こうした取り組みの背景には、20世紀後半に起きた競馬界の変革があった。ブリーダーズカップやジャパンCといった既存イベントの成熟、シェイク・モハメドによるゴドルフィンの設立と大陸間のレースをターゲットにする世界戦略、ドバイワールドカップ開催の成功、欧州馬のメルボルンカップ遠征、そして1998年モーリスドゲスト賞でシーキングザパールが海外G1初制覇を果たした日本競馬の台頭などである。
国際的な遠征を促進するための短命プロジェクトもあった。グローバルスプリントチャレンジ、アジアマイルチャレンジ、エミレーツワールドシリーズといった取り組みである。
そうした流れの中で、日本調教師の海外遠征は積極性を増し、日本馬が世界の一線級と互角に戦えることを証明してきた。
それ以来、国際的な遠征は一般的なものとなり、むしろ競馬界にとってますます重要になっている。多くの地域で競馬は他のスポーツや余暇産業との競争に苦戦しているが、その中で日本の参加はますます重要な意味を持つ。英国やアイルランドの競馬場は低い賞金水準という制約を抱えながらも、長年かけて築いてきた関係性と一流の競馬体験の提供により、一定の成果を挙げている。
「私たちが学んだ最大の教訓は、今年の馬や今日話している馬主や調教師が重要なのではなく、将来遠征に適した馬を持つであろう彼らが重要だということです」とスミス氏は言う。
「長期的な視点で取り組むことが重要なのです」