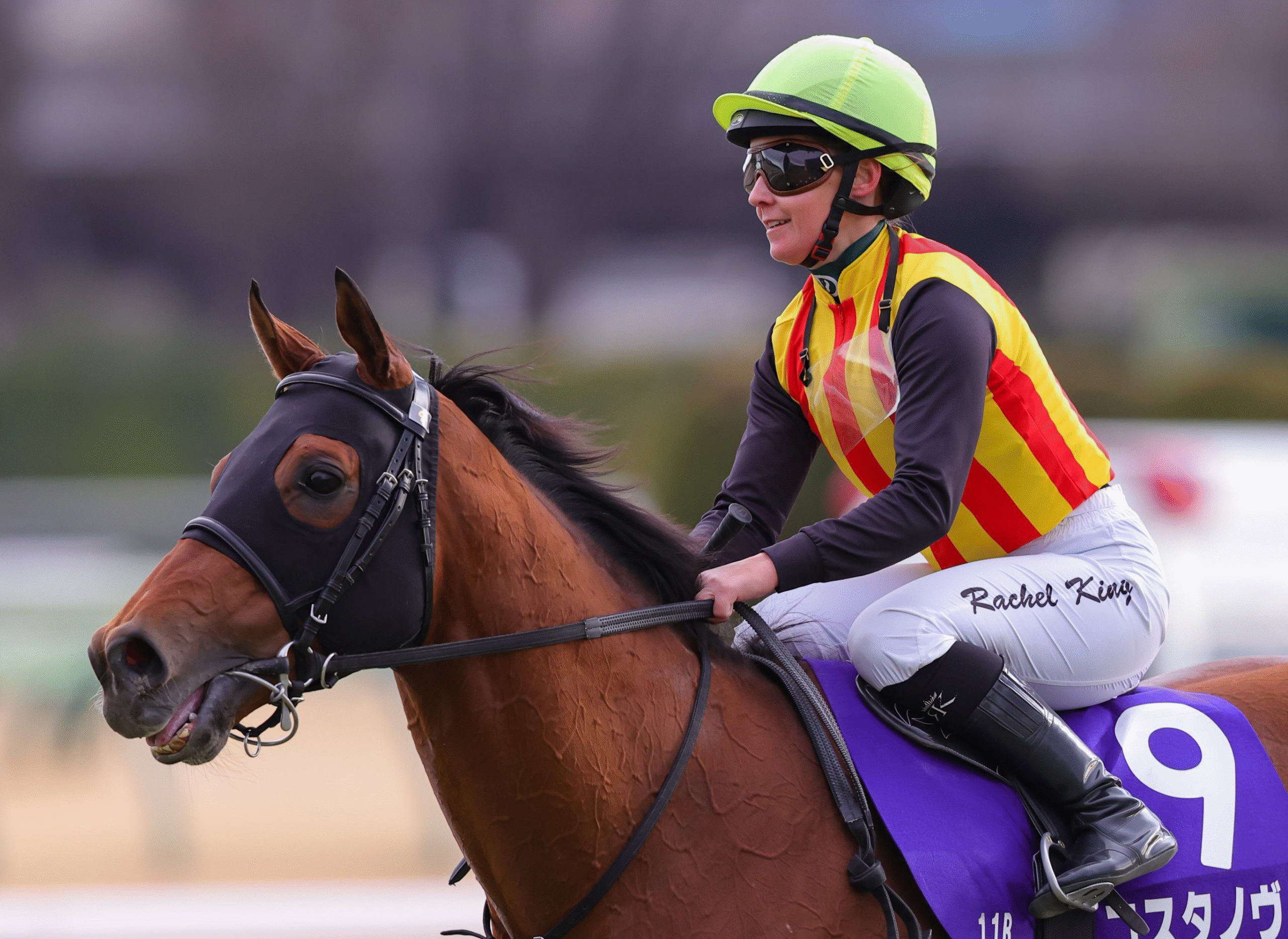達城龍次騎手はここ1年の間に、遅咲きの花を咲かせつつある。
2023年7月にシュアゲイトで大井競馬場のS3・サンタアニタトロフィーを勝って重賞初制覇。今年はグレースルビーで笠松のSP1・ブルーリボンマイル、名古屋のSP1・若草賞土古記念を制した。
現在、45歳の達城騎手は肩から上にピンク色の『鋸歯形』が入った、黒い勝負服を着用している。2024年7月11日、その勝負服を着て大井競馬場の第2レースを勝った直後に、Idol Horseの取材に応じてくれた。
この日は12レースでも勝利を挙げており、今年のシーズン勝利数を26勝に伸ばした。1996年の6月8日に17歳で騎手デビューし、その2ヶ月後に初勝利を挙げて以来積み重ねた地方競馬通算勝利数は、この日までに673勝を記録している。
しかし、大井競馬場が誇る有名なベテラン騎手となるまでの道のりは、祖父に調教師を持つ家柄としては異例のものだった。そして、競馬場やレース映像をドローンで撮影する企業の創業者としての一面を持つ彼は、今でも騎手として異色の存在だ。

異色のキャリア
達城騎手は競馬一家出身にもかかわらず、競馬場や厩舎で幼少期を過ごしたわけではなかった。子役として舞台やカメラの前で活躍し、いくつかのテレビドラマにも主演している。
「2歳のとき、親が勝手に劇団に入れて(笑)」
彼は笑いながら、子役になった経緯を明かす。その後しばらくして、役者の道を「才能が無かった」として諦めた。もう一つ取り組んでいた野球も、この頃諦めている。
家族に競馬関係者がいる騎手は、幼い頃から馬に関わることが多い。しかし、達城騎手は祖父が調教師として川崎競馬場で働いていたにもかかわらず、子供の頃に競馬場を訪れた経験は一回しかない。
「川崎競馬場とは別の自宅を持っていたので、自宅の方に住んでいました」
「ある時テレビを見たときに、当時のオグリキャップとか武豊さん(伝説の1990年有馬記念)を見ました。第二次競馬ブームとか、そんな感じの時期ですよね」
「その時にやっぱり『これしかないな』と思いました。一目惚れって奴ですね。体も小さかったので。祖父が川崎競馬場で調教師をしてたんですけれど、それとは関係なく育ってきたので。ほぼ影響は受けず、本当にテレビの影響だけです」
ファンや視聴者に新たな体験を提供する会社を営んでいる理由も、納得できる。バイアリーターク・インダストリーズという彼が創業したベンチャー企業は、怪我を負い、鞭を置いた後のキャリアを考えるようになったときに生まれたアイディアだという。
競馬学校では、騎手にならなければ教育の代わりにはならないという現実を突きつけられた。当時は高卒の資格も持っていなかったので、28歳で通信制の高校に入学し、3年間で無事に卒業した。その後、通信制の大学に入学したが、大井での騎手の仕事との両立は難しいものだった。
「在籍は2年間位してましたけど、ほぼ行ってないですね、忙しくて。ごめんなさい」
「数年前怪我もしたりして、もしかしてこのまま引退になるかもしれないっていう時期があったので、そのときに起業の考えが生まれました。海外競馬を色々見てるのですが、そこではドローンはやっぱり頻繁に使われていました。ですが、なかなか日本では見られなくて」
「日本はJRAでヘリ飛ばしてるイメージがあるんですけども、向こうでは積極的にドローンを取り入れる動きがありまして。そういうとこに目をつけて、これから日本でも来るのかなって思いました。とりあえず起業をして、準備をしていました」
この事業は電波法や航空法など、ドローンを規制する日本の厳しい法律を守らなくてはいけない。他の国と比べて、日本はドローンの使用が容易という環境ではない。
「でもいずれはそうなってくるんじゃないかなと期待はしてます」
今日まで良馬場。明日からTCKです。 pic.twitter.com/p8L3fbw8ae
— 達城龍次 RyujiTatsushiro (@tatsushiroryuji) May 12, 2024
アメリカ競馬の先駆者
達城騎手は世界の競馬にも目を向けており、地方競馬が北米の競馬から学びを得ていることを興味深く見ている。
「アメリカや海外に寄せてきた感じがすごいありますよね。昔は本当に地方競馬という感じだったのですが、その辺はすごく進歩したなっていう感じはしますよね」
東京シティ競馬のトゥインクルレースから世界に旅立った、マンダリンヒーローもその一頭だ。2023年のアメリカG1・サンタアニタダービーではハナ差の2着という驚異のパフォーマンスを見せ、JRAのフォーエバーヤングが3着に健闘した年よりも1年先にケンタッキーダービーに挑戦した。
達城騎手自身、何年も前にアメリカ競馬に挑戦したことがあるが、当時はマンダリンヒーローやフォーエバーヤングが登場した今と違って厳しい時代だった。今では日本の馬や騎手は大きく進歩しており、それを嬉しく思っていると話す。

「当時、アメリカに行った頃は考えられないことでしたよね。最近は皆さん積極的に海外に行かれてて、世界の舞台でも戦えるようになってきてると思ってますね」
今から21年前、アメリカに長期滞在した際は、ペンナショナル、デラウェアパーク、ローレルパークといった競馬場で現地の競馬を学んだ。メリーランド州フェアヒルに厩舎を構えていた殿堂入り調教師、ジョナサン・シェパード調教師の下でも働いていたが、当時は自らの厩舎で200頭近くを管理していたという。まさに、大井の厩舎とは別世界だった。
「シェパード調教師は結構厳しく、厳格な方でした。なかなか笑顔も見せない方でしたね」
「彼の厩舎で働いたり、彼が持っていた競馬場の方で働いたりと、数ヶ月に渡って色々と働かせてもらっていました。競馬場に行ったり、牧場で働いたりしましたが、20年以上前の当時の日本競馬とアメリカ競馬は大きな差があると感じました」
「カルチャーショックを受けまして、何かいいものを持ち帰れたらいいなと思って熱々やっていましたね。本当に凄かったです。常に競馬っていうものが完璧に出来上がっている状態ですよね。今の日本は海外に似せて段々段々頑張っていってる感じですけど、当時のアメリカではそれがもう昔から出来上がってる感じでしたね」
そこでは、殿堂入りジョッキーたちとも出会った。ラモン・ロドリゲス元騎手と仲が良く、バーに連れて行ってもらったり、色々な人を紹介してくれたという。今でも当時の出会いに感謝しているというが、デラウェアパーク競馬場でジェリー・ベイリー元騎手に叱られた思い出もあると話してくれた。
「重賞でデラウェア・パークに乗りに来たときに、僕は普通にお客として競馬場に来ていました。『サインください』と言ってレーシングプログラムを渡したのですが、ペンを持っていなかったので『サインもらうのになんでペン持って来ないんだ!』って怒られた記憶があります(笑)」
当時を振り返り、笑いながら思い出を語ってくれた。

次の挑戦は調教師?
達城騎手のキャリアは『殿堂入り』というレベルではないかもしれないが、ここまで成功を収めてきた。競馬場の内外で自身の腕を磨く努力を続けてきたが、40代半ばに差し掛かり、騎手としての残りの時間が少ないことも自覚している。
「まだ体力の衰えは感じていませんが、今は若手も出てきてます。大分肩身が狭い感じにはなってきていますね」
「調教師免許の試験は長年挑戦していますが、現状調教師も多いので、なかなか合格には至っていません」
では、次の仕事は調教師なのだろうか?
「やはり、そうですね。調教師は魅力的な仕事だと思ってるので、そっちでも成功したいなと思っています」
彼は自らの選択で競馬の世界に入り、独自の道を歩んできた。しかし、今の達城騎手は祖父と同じ道を歩みつつあるのかもしれない。