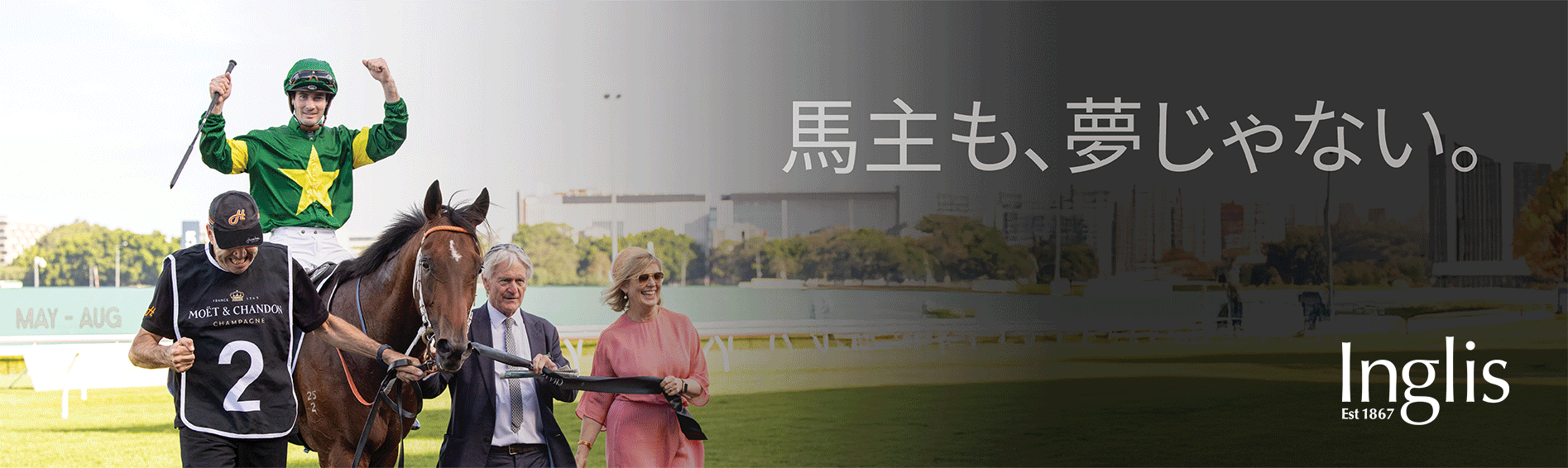競馬史を彩る「2頭の名勝負」。フォーエバーヤングとロマンチックウォリアーが繰り広げた2024年サウジカップの死闘は、一騎打ちの名勝負を語る上でどのような評価を受けるのか?
まず、今回のランキングの基準を整理しておこう。
ここで選ぶのは、あくまで『2頭の戦い』に焦点を当てたレースであり、三つ巴やそれ以上の接戦は対象外とする。選考のポイントは、それぞれの馬の実績とレースの重要度、さらにはレース前の期待値の高さだ。
しかし、何よりも重視したのは、レース本番で繰り広げられた一騎打ちの激しさである。勝負根性をぶつけ合い、どちらも譲らぬ展開となったレースを厳選した。現代競馬の歴史において、こうした名勝負は数多く存在する。
その中から、特に印象的な5レースを選び抜いた。
5. 2003年 タンクレッドS – フリーメイソン vs ノーザリー
この一戦は、事前に2頭の対決として大きく注目されたわけではなかった。だが、ゲートが開くと下馬評を覆す激戦が開幕、競馬史に残る壮絶なマッチレースへと発展した。
当時のオーストラリア競馬界を牽引していたノーザリーは、2003年シーズンすでに二度目のコックスプレートを制し、アンダーウッドS、コーフィールドC、オーストラリアCと立て続けにG1タイトルを獲得していた。まさに向かうところ敵なしの勢いだった。
ところが、シドニー遠征に入ると、右回りのレースで意外な苦戦を強いられる。
G1・ランヴェットステークス(2000m)では、リパブリックラスの激走に屈し、ハナ差の2着。そして、G3・マニオンカップ(2400m)では重い斤量を背負い、主戦騎手のパトリック・ペインが慎重な騎乗を選択した結果、直線で進路を塞がれたまま6着に沈んだ。
次に迎えたレースがオーストラリアで唯一の定量戦G1であるタンクレッドS(2400m)。この時点でノーザリーの評価は依然として揺るぎなく、単勝1.45倍の圧倒的な支持を受けていた。ペインは運任せの展開を避けるため、主導権を握る競馬を選択。先行するセントレイムスの外につけ、スムーズにレースを進めるかに思われた。
しかし、この展開を見逃さなかったのがダレン・ビードマン騎手だった。タフなステイヤー、フリーメイソンを巧みに押し上げ、ノーザリーの外から並びかける積極策に出た。
ペインはスローペースの流れに持ち込むことを考えていたかもしれないが、ビードマンは一貫したペースを刻み続けた。
驚くべきことに、1700m地点から2頭は一度も1馬身以上離れることがなく、1000mを切ると互いに頭差以内の攻防が続いた。まさに「2頭の死闘」と呼ぶにふさわしいレースだった。
伝説的な実況アナウンサー、イアン・クレイグは、500mを通過する際に『まさに一騎打ち(hammer-and-tong)』と形容し、その激闘の本質を見事に言い表した。
『ファイティング・タイガー』の異名を持つノーザリーが意地を見せたものの、最後の直線ではフリーメイソンの底力が勝り、壮絶な叩き合いを制した。
4. 1996年 阪神大賞典 – ナリタブライアン vs マヤノトップガン
G2・阪神大賞典(3000m)は、天皇賞・春(3200m)への前哨戦として位置づけられることが多い。だが、1996年の一戦はそれだけではなかった。過去2年の年度代表馬同士の激突として、大きな注目を集める一戦となった。
ナリタブライアンは、1994年にクラシック三冠を制し、有馬記念も勝利。圧倒的な強さを誇ったそのシーズンの実績が評価され、年度代表馬に選ばれた。しかし、4歳になってからは阪神大賞典こそ勝利したものの、それ以外の3戦では敗れ、完全復活には至らなかった。
その間に、次なる王者として台頭したのがマヤノトップガンだった。1995年の菊花賞と有馬記念を制し、その有馬記念ではナリタブライアンを4着に退けている。その実績が評価され、1995年の年度代表馬の座を手にした。
レース前からこの2頭の対決に注目が集まった。人気は僅差で、マヤノトップガンが単勝2.0倍、ナリタブライアンが2.1倍と拮抗していた。
レースが期待通りになることは滅多にないが、この時は期待通りとなりレースは2頭の戦いとなった。前半、マヤノトップガンと田原成貴騎手は5番手の外目に位置し、その1馬身後ろに武豊騎手のナリタブライアンが続く。スローペースの流れの中、田原はじわじわと進出し、800mを切るとマヤノトップガンを先頭に押し上げる。600mを過ぎたところで武は外へ持ち出し、ここで真っ向勝負が始まった。
3〜4コーナーでナリタブライアンがわずかにリードしたようだが、武は手綱を動かし続け、一方の田原はまだ余裕を持って追い出しを待っていた。直線に入ると田原が本格的に仕掛け、マヤノトップガンが再び前に出る。残り200mでは、マヤノトップガンがクビほどリードを奪い、ナリタブライアンを振り切るかに見えた。
しかし、このレースは最後の最後まで勝負が分からなかった。ここからナリタブライアンが驚異的な粘りを見せ、ゴール前で再び並びかける。残り数完歩までマヤノトップガンがリードしていたが、ゴール寸前で不屈の闘志を見せたナリタブライアンが武の手腕に導かれわずかに差し返し、頭差の劇的勝利を収めた。
3. 2025年 サウジカップ – フォーエバーヤング vs ロマンチックウォリアー
歴代の名勝負のようなゴールまで一歩も譲らぬ競り合いではなかったが、間違いなく記憶に残る壮絶な2頭の戦いとなった。
レース前から注目度は高かった。史上最高賞金獲得馬にして芝王者とも言えるロマンチックウォリアーが、世界最強のダートホースと称されるフォーエバーヤングに挑む構図。
ロマンチックウォリアーは3番枠、フォーエバーヤングは大外14番枠からの発走。この枠順を考えれば、勝負所は終盤になると思われた。だが坂井瑠星騎手は果敢な策に出る。スタート直後にフォーエバーヤングを一気に馬群の前へ押し上げ、100m地点で先行集団の外につけると、その直後にロマンチックウォリアーを封じ込める形となった。
長いバックストレッチではロマンチックウォリアーがフォーエバーヤングを追走。そして、注目の場面が訪れた。ジェームズ・マクドナルドはインから外へと持ち出し、一気に加速をつけながらフォーエバーヤングを捉えにかかったのだ。
直線に入るとロマンチックウォリアーが先頭へ。誰もがそのまま押し切ると思った。だが、他の馬では難しかっただろうが、フォーエバーヤングは違った。
粘り強さ、スピード、底力、全てを兼ね備えたこの馬は、まさに異次元のタフさを見せた。ゴール直前でロマンチックウォリアーを差し返し、世界最高賞金のレースを制した。
2. 1989年 プリークネスステークス – サンデーサイレンス vs イージーゴア
サンデーサイレンスとイージーゴアの1年間にわたる激闘は、競馬史上屈指のライバル対決として語り継がれている。アメリカでは『世紀のレース』としてブリーダーズカップクラシックが取り上げられることが多いが、両馬の戦いとして最も白熱したのはプリークネスステークスだろう。
この対決は米国内の東西対決の様相も呈していた。そして2頭が初めて相まみえたのがケンタッキーダービーだった。イージーゴアが圧倒的1番人気に支持されたが、単勝オッズ4-1(5倍)の2番人気だったサンデーサイレンスが2馬身半差で快勝。しかし、その結果は「泥んこ馬場に助けられた」と評価され、イージーゴアの評価は依然として高かった。
迎えたプリークネスSは快晴のもと、良馬場で行われた。イージーゴアは再び1番人気(1.6倍)、サンデーサイレンスは2番人気(3倍)。
序盤、パット・ヴァレンズエラ騎手のサンデーサイレンスは3番手の外に位置し、その直後にパット・デイ騎手のイージーゴアが追走。この体勢のまま半マイルを通過し、サンデーサイレンスが少しずつ前進し始めたが、ここでデイが動く。サンデーサイレンスを内に閉じ込めるようにして、先頭のヒューストンをかわしにかかったのだ。
デイの戦略は一見、見事な一手に思われたが、外から勢いをつけたサンデーサイレンスに対して静観の構えを取ったことで、そのアドバンテージを失うことになった。結果として、2頭は最終コーナーの終わりで完全に並び、全く互角の勝負となった。
そこから繰り広げられたのは、競馬史に残る壮絶な直線の叩き合いだった。イージーゴアが残り1ハロン地点でわずかに頭差抜け出し、ゴールを過ぎた瞬間には前に出ていたようにも見えた。しかし、肝心のゴール板ではサンデーサイレンスがハナ差先着していた。
その後、イージーゴアはベルモントステークスを8馬身差で圧勝し、サンデーサイレンスの三冠を阻止。しかし、2頭の宿命の対決はブリーダーズCクラシックで再び実現し、今度はサンデーサイレンスが再び僅差で勝利を収めた。
1. 1986年 コックスプレート – ボーンクラッシャー vs アワウェイバリースター
オーストラリア、ニュージーランドの競馬ファンに『世紀のレース』と言えば何かと尋ねれば、ほぼ間違いなく1986年のコックスプレートが挙げられるだろう。
ボーンクラッシャーは1985-86シーズンの豪・NZ両国の最優秀3歳馬。一方、アワウェイバリースター(NZではウェイバリースター)は、ニュージーランドで破竹の勢いで勝ち上がり、豪州遠征に挑んでいた。
レース前から激戦は必至と見られていたが、実際にはそれをも凌駕する壮絶な一騎打ちとなった。この名勝負をさらに際立たせたのが、オーストラリア競馬史に残る名実況を残した名アナウンサー、ビル・コリンズの存在だった。
アワウェイバリースターは、ムーニーバレー競馬場のタイトなコース形態に苦しみ、前半1000mで外々を回る形に。一方、ボーンクラッシャーも馬群の間に挟まれ、ストライドの大きいタイプの彼にとって決して理想的な位置ではなかった。
800m地点のコーナーで、ゲイリー・スチュワート騎手がボーンクラッシャーを外へ持ち出し、一気に進出を開始。これを見たランス・オサリバン騎手のアワウェイバリースターもこれに並びかけた。ここから、かつてない激闘が始まる。
両馬が馬群を突き放して並走する中、コリンズはマイク越しにこう問いかけた。
「これは早仕掛けではないのか?」
直線に向いて先に手応えが良かったのはアワウェイバリースター。200mの激しい攻防の末、ボーンクラッシャーが半馬身遅れ、スチュワートの鞭も必死に動いた。
しかし、ここでボーンクラッシャーが底力を発揮。猛烈な鞭の連打に応え、直線に入ると再び頭を並べた。今度はオサリバンが追いにかかると、アワウェイバリースターが再び半馬身リード。
観衆の大歓声を背に、残り50m地点ではアワウェイバリースターがわずかに優勢。そのまま押し切るかに思われたが、どこかでボーンクラッシャーが必ず届くという予感が漂っていた。
そして、その瞬間が訪れた。ゴールまであと数完歩というところで、ボーンクラッシャーがついに前へ出る。名実況ビル・コリンズの言葉を借りれば、「歴史にその名を刻む」勝利を手にしたのだ。
着差はわずかに首差。それでも、この壮絶な一騎打ちが競馬史上屈指の名勝負として語り継がれることに、疑いの余地はなかった。
惜しくも選外、次点の名勝負
1938年 ピムリコスペシャル – シービスケット vs ウォーアドミラル
史上最も有名なマッチレースを挙げずにはいられない。ラジオ時代を象徴する伝説の一戦、1938年のピムリコスペシャル。シービスケットとウォーアドミラルの対決はアメリカ全土の注目を集め、ホワイトハウスには特別に中継が入れられ、ルーズベルト大統領もその激闘を追ったという。
1975年 キングジョージ6世&クイーンエリザベスS – グランディ vs バスティノ
アスコットの最高峰のレースで繰り広げられた手に汗握る攻防は、トップ5入り目前の名勝負だった。ダービー馬の3歳馬が、セントレジャー馬の4歳馬を歴史に残る直線の叩き合いでねじ伏せた。
2000年 香港マイル – サンライン vs フェアリーキングプローン
デヴィッド・ラファエルの名実況が熱戦をさらに引き立てた一戦。『世界の名牝』は、沙田競馬場に響き渡るフェアリーキングプローンへの大歓声をものともせず『香港の英雄』を振り切って勝利を収めた。
2001年 アイリッシュチャンピオンS – ファンタスティックライト vs ガリレオ
30年間にわたり、国際競馬はゴドルフィンとクールモアの戦いとして展開されてきた。そしてこの一戦も、その歴史にふさわしい激闘となった。ゴドルフィンの世界を股にかける5歳馬が、クールモアの革新をもたらした3歳馬を封じ、キングジョージで喫した2馬身差の敗北を6週間後に見事に覆した。このレースが、ガリレオにとって初めての黒星となった。
2014年 香港ダービー – デザインズオンローム vs エイブルフレンド
この一戦は直線でディバヤーニも加わる場面があり、三つ巴の戦いと捉えられるかもしれない。しかし、このレースの本質は、クラシックシリーズを席巻したトップ4歳馬2頭による壮絶なマッチレースだった。その後の両馬の活躍を考えれば、この激闘の価値はさらに際立つものとなった。