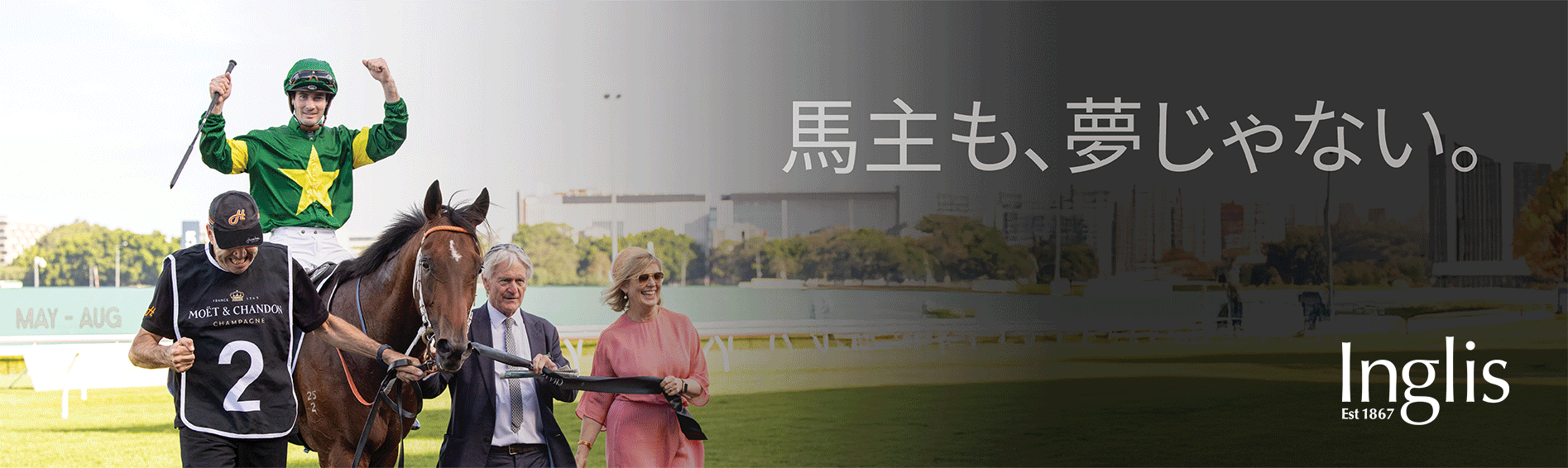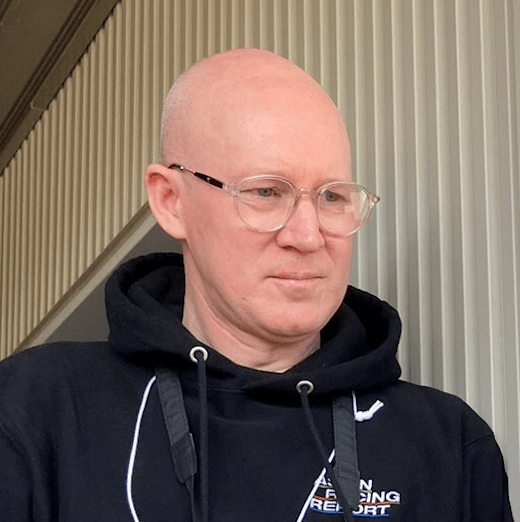ウンベルト・リスポリ騎手はカリフォルニアの自宅に戻っているが、ジャーナリズムの首にかけられた黄色いアラゲハンゴンソウの花冠に膝が触れてから2日が経った今も、キャリアの節目となる勝利を静かに振り返る余裕はない。
「プリークネスを勝てたなんて、本当に信じられないくらい素晴らしいことです」と彼は語る。
「レースの後には記者会見やインタビューがあって、それが終わったら、会いに来てくれた人たちにちゃんと対応して、その瞬間をみんなと一緒に楽しみたかったんです。サインをして、写真を撮って…ああいう時間はずっと待ち望んでいたものだから、みんなと共有したかったんです」
先週土曜の午後、ジャーナリズムがゴスジャーを差し切って劇的な勝利を収めて以来、リスポリには息つく暇すらなかった。彼はまず家族を連れてジャーナリズムの馬房を訪れた後、アメリカ三冠競走で初めての勝利を挙げたイタリア人騎手として、ようやく競馬場を後にし、勝利に沸く関係者たちとともに夕食へと向かった。
その後はホテルに戻って短い休息を取り、妻のキンバリーさんと幼い息子二人と共に2時間ほど眠っただけで、朝6時の便でボルチモアからロサンゼルスへと飛び立った。
日曜の午後にはサンタアニタ競馬場で5鞍に騎乗し、そのうち1勝を挙げたのは、ジャーナリズムの管理調教師であるマイケル・マッカーシー師の管理馬だった。
「日曜の夜、さすがにぐったりしてすぐ眠れるかと思ったんですが、それでも眠れなかったんです」
「プリークネス当日の朝7時からずっと起きていて、帰りのフライト中も一睡もせず、24時間以上起きていた上に馬にも乗っていました。月曜の朝5時半にはまた起きて、来週の重賞に向けて3頭の調教に騎乗しました」
「今日が終わったら」と彼は笑いながら続けた。「しばらく携帯電話を放っておいて、ようやく家族との時間を楽しもうと思います」
確かに疲労は溜まっている。だがそれでも、もう一度同じことをやれと言われたら、彼はきっと同じ道を選ぶだろう。情熱的なナポリ出身の勝負師にとって、あの批判は決して容易に受け入れられるものではなかったが、プリークネスのタイトルが自身のキャリアに加わるのであれば、その価値は十分にあった。
ジャーナリズムが三冠の第2戦で勇敢な勝利を収めた直後、リスポリは感情を抑えるのに苦労した。2週間前のケンタッキーダービーでの2着という悔しさを癒してくれる一勝だった。
ピムリコの直線で主役たちがぶつかり合ったあの一戦は、まるで剣闘士同士の決闘のようでもあり、一方でレース後の論争がその歓喜にやや水を差した。
ウンベルト・リスポリ騎手による場面ごとのレース回顧(英語版)
リスポリ騎手は内ラチ沿いの距離を稼ぐ進路を選び、狭いスペースを果敢に突いた。その隙間が閉じかけても彼は動じることなく、そこからの数完歩の間、まるで遊園地のゴーカートのような押し合いが繰り広げられた。
この大胆な進路選択については、NBCやFox Sportsのコメンテーターから、YouTubeの熱心な分析者、そしてX(旧Twitter)の『ネット戦士』に至るまで、自称専門家や素人評論家たちによって徹底的に検証され、論じられている。
一部では、ジャーナリズムは降着になるべきだった、リスポリ騎手には処分が下されるべきだったという声も上がった。なぜなら彼が外側にいたフラヴィアン・プラ騎手のゴールオリエンテッド、そして脚色が鈍ったクレバーアゲインとの狭い隙間を強引に突こうとしたためだ。ゴールオリエンテッドは内に寄れてジャーナリズムと接触し、その反動で横に弾かれてしまった。
他にも、リスポリの判断力に疑問を呈し、二度のイタリアチャンピオンに輝いた彼がまるで迷走していた、判断が定まらず、パニックに陥っていたのではないかとする指摘もあった。
「瞬きすらしなかったよ。あそこに突っ込むと決めたし、もし(フラヴィアンが)肘を張って通さないようにしたとしても、それでも突っ込むつもりだった」
「レース後なんて何とでも言える。『降着になるべきだった』『荒っぽい競馬だった』『パニックだった』ってね。でも、僕はまったく動揺していなかった。騎手が本当にパニックになってるかどうか分かる瞬間ってのはある。進路に片足を突っ込んで、それでもうやめて戻ってくる。あれがパニックしてる証拠。でも僕は足を踏み入れたとき、何をすべきかは完全に分かっていた」
リスポリによれば、向こう正面でジャーナリズムの手応えは思ったほど良くなく、1番人気馬にもかかわらず、早くから追っていかねばならなかったことに驚いたという。その時点での動きの鈍さが、このレースの展開を大きく左右することとなった。
「すべてのレースが想定どおりにいくわけじゃない」とリスポリは説明する。
「もし誰かが『リスポリの馬は半マイルで失速していた』なんて予想してたって言うなら、それは嘘だって言ってやる。誰も、彼が手綱を放して走るような状態を失って、僕が全力で追っているなんて想像しなかっただろう」
「だから、僕は二つの可能性を考えた。馬が力を出せないのか、それともただリラックスしすぎてるだけなのか。外に出してみれば何か反応してくれるかもしれない、ケンタッキーダービーのときみたいに『そろそろ行く時だ』って思ってくれるかもしれない、そう思って外に出そうとしたんだ。でも彼は反応してくれなかった。どんなにしても、あの時点では手応えがなかった」
「どこにも行ける状態じゃなかったから、次に考えたのは『もしこの馬に力がないなら、大外を回したって何の得にもならない』ってことだった。その瞬間に判断しなきゃいけない。僕はもう、気持ちの余裕なんてなかった。賢く立ち回ろうなんて思ってもいなかったし、あの状況なら、もし少しでも距離を稼げるチャンスがあるなら、それに賭けるべきだと思ったんだ」
その進路取りによって、リスポリはプラのゴールオリエンテッドの内側、すなわち最終コーナー手前のポジションに入り、前にはクレバーアゲインとゴスジャーが並走していた。
「これまでジャーナリズムに騎乗したすべてのレースで、いつも僕はラスト3ハロンから早めに追い出さなきゃいけなかった。そこから手を動かして、積極的に動かしていく馬なんだ。でも、土曜日の彼はいつもより怠けていた。だけど、尻に一発くれてやればスイッチが入る、そういう馬だってことはよく分かってたんだ」
「でもその時点、つまり4角手前で僕が考えていたのはこうだ。ホセ(オルティス)がクレバーアゲインでペースを上げる、ルイス・サエスが乗るゴスジャーがそれに並走する、そしてフラヴィアン(プラ)は当然3頭分外に持ち出してゴスジャーの外を回る、そうなったら直線入り口で僕はフラヴィアンのさらに外に出られるだろう、と」
「ところが、ホセの馬が止まって、フラヴィアンは外に動いたけどその馬も下がり始めて動けなくなってしまった。そこからフラヴィアンは再び内に戻ろうとしてきた。でも、その時点で僕はもうそこに足を踏み込んでいた。だったら、僕にどうしろって言うんだ?」
そのとき、ゴスジャーがスパートをかけて抜け出しにかかる中、リスポリ騎手とジャーナリズムは、失速したクレバーアゲインとプラ騎手が騎乗するゴールオリエンテッドの間に挟まれ、両側から圧力を受けて勢いを大きく削がれてしまった。
「これが『実戦の騎乗』なんだ」
「イタリアだったら、みんなこの騎乗を称賛してくれると思う。ああいうのが僕らのやり方なんだ。確かに、あそこに突っ込むのはリスクだったけど、それも競馬の一部だよ」
「それに言ったように、最初から内しかないと思ってたわけじゃない。もしゴールオリエンテッドがサエスの外にすぐ動いてくれていたら、僕は彼のさらに外に出たはずだ。あの狭い隙間を突こうなんて、絶対に思わなかったよ。ちゃんと進路が開けていれば、そっちに出ていた。バカじゃないんだから」
「芝コースだったらそうしたかもしれない。芝なら無理して行かない。でもダートではそのリスクは取れない。とはいえ、あの時点ではもう進路に入っていたし、自分が何をしているかは分かっていた」

リスポリはすでに、三冠最終戦であるG1・ベルモントステークスを見据えている。今年はベルモントパークが改修中のため、例年より短いサラトガの10ハロン(約2000m)で行われる。その舞台でケンタッキーダービーの1着馬ソヴリンティ、3着馬バエサとの再戦が実現することを彼は期待している。両馬はプリークネスには出走しなかったからだ。
「ダービーのときみたいな不良馬場じゃなくて、乾いた馬場でみんなが出てくるのを見るのは面白いと思う。厳しい戦いになるよ。うちの馬は3週間で立て直す必要があるけど、ソヴリンティとバエサはそれより数週間多く休めるし、1戦分の負担も少ないからね」
「(彼らがプリークネスに出ていれば)競馬界にとっては良いことだったかもしれない。でも僕は、調教師の判断を否定するようなことは決して言わない。調教師がそう決めたのなら、それは尊重されるべきだ。特にビル・モットやジョン・シレフスのような調教師が行かないと判断したのであれば、そこにはきっと理由があるんだよ」
リスポリは、ジャーナリズムのために尽力してきた多くの仲間たちの存在を強調した。それは、マイケル・マッカーシーや、オーナーであるエクリプスサラブレッド、ブライドルウッドファーム、ドンアルベルトステーブル、ラペンタ、エレインステーブル5、クールモアのパートナーらにとどまらず、厩務員、調教助手たちにまで及ぶ。
「長年支えてくれたマイケル・マッカーシーとこの勝利を分かち合えたことを誇りに思います。厩務員のロランド、調教に騎乗してくれたマーク、助手のフェリペ、オニール、ジャスティン、そしてケンタッキーやカリフォルニアで関わってくれているすべてのスタッフ。これは大きな『チームの勝利』であり、この人たちと一緒に勝てたことが本当にうれしい。お互いを支え合い、助け合って、ベストを尽くすために力を合わせてきたからこそ得られた結果です」
「さあ」と彼は続けた。「そろそろバッテリーを充電して、ひと眠りしないとね」