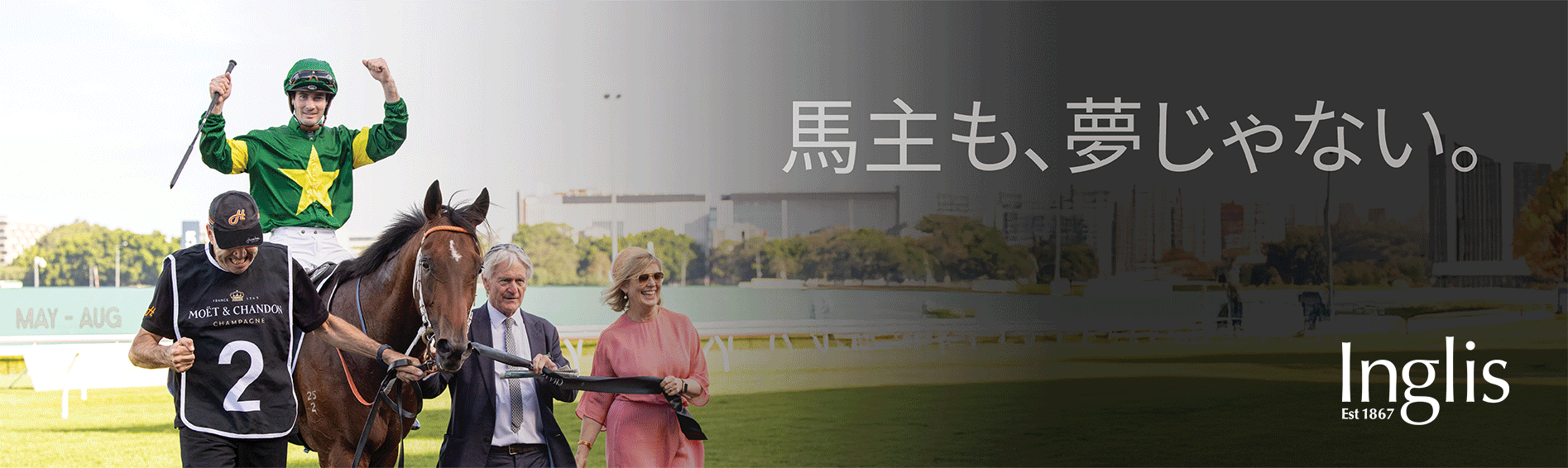北海道、社台スタリオンステーション(社台SS)。ここはたとえ初めて足を踏み入れたとしても、なぜか“見覚えある風景”が広がっている。
たとえるならば、2003年頃のマドリード、サンティアゴ・ベルナベウのホームのロッカールームに入るようなものかもしれない。左に座るジダン、右でスパイクの紐を結ぶロナウド。ロッカーにもたれながら、ロベルト・カルロスがデビッド・ベッカムやルイス・フィーゴと談笑している。見渡しても、振り向いても、あのレジェンドがいる。
だが、白いユニフォームはここにはない。あるのは艶やかな馬体、サッカースパイクの代わりにあるのは蹄だ。
社台SSの種牡馬たちは、まさに“銀河系軍団”だ。一流の血統と気性、そしてトップクラスの種牡馬を繋養するために編成された、種牡馬の殿堂である。

そして、厩舎のいちばん奥。磨かれた真鍮の向こう、北海道の空から差し込む柔らかな冬の光の向こうに、通路全体の空気をガラッと変える一頭の馬が立っている。
扉にいちばん多くの“勲章”が飾られているのも、その馬だ。熱狂的なファンの軍勢から贈られた品々である。オルフェーヴルだ。
個性が燃え立つ栗毛で、いたずら心に包まれた天才。頭を少し動かすだけで周囲の空気が変わるようなアスリートである。社台SSの三輪圭祐氏は、敬意と可笑しみ、そして少しばかり感謝にも似た響きを混ぜながら、彼について語る。
「誤解のないように言うと、オルフェーヴルは乱暴な馬ではありませんし、クレイジーというわけでもありません。天才型です。ただやんちゃで、いたずらっ子で、いつまでも若いんです」と三輪氏はIdol Horseに語った。
三輪氏にとってオルフェーヴルは、単なる種牡馬ではない。先生である。
「彼はいつも自分のやりたいことをやっています。自己表現をするタイプです」
「オルフェーヴルを見ていると、時々、自分の人生について考えたくなります」
引退してからも人を変えてしまうアスリートは多くない。だがオルフェーヴルは、今もそれをやってのける。
三輪氏が彼を人間のように見るのは、ある意味でオルフェーヴルが、学校でいちばん印象に残る子どものように振る舞うからだ。規則に従わず、それでいて毎日のように教室の空気をひっくり返してしまう、あのタイプである。
「もしオルフェーヴルが人間だったら?」との問いに、三輪氏は少しの間を置く。
「IQは高いタイプでしょうね……。オルフェーヴルは学ランを着なかったり、ボタンを開けっぱなしにしたりするでしょうね。たまに学校に来なかったり、授業中に寝たりもするけど、試験はすごく良い点を取ると思います」
校則破りの天才、まさに完璧な表現だ。決して悪意はなく、そして忘れられない。社台SSは彼に合わせて形を整えなければならない。
「オルフェーヴルはちょっかいかけて遊ぶのが好きで、他の馬に絡みたがるので、他の馬とあまり関わりを持たせたくないんです」
オルフェーヴルは、挑発できる相手が少なく、厩舎内の“馬の政治”に火をつける機会も少ない角の場所にいる。隠すためではない。ただ、ロッカールームの残りの部分が機能するようにするためだ。
オルフェーヴルという馬の本質はそこにある。彼は厩舎の一部であるだけではない。厩舎のエネルギーそのものを規定する存在なのだ。


もしオルフェーヴルが破天荒型なら、亡きディープインパクトは優等生代表だった。オルフェーヴルが限界に挑戦する一方で、ディープインパクトはそれを本能的に理解していた。オルフェーヴルが先生に挑む子どもなら、ディープインパクトは先生が静かに頼りにする子どもだった。
三輪氏はその対比を語るとき、出てきた言葉は即答だった。
「ディープインパクトとは仲良くなれないと思います。ディープインパクトは生徒会長になるタイプですね」
この比較は、どちらの馬を優劣を付けるためのものではない。偉大さがいかに違う形で現れ得るかを示し、そしてここにいる熟練の担当者たちが、それぞれを個として扱い、性格や長所と短所について深く考えていることを物語るものだ。
ディープインパクトは落ち着いていて、状況を理解し、絶えず集まる人だかりやカメラにも、政治家のような品格で対応できた。オルフェーヴルは、世界に合わせることを拒む自由思想家だ。ディープインパクトはすべてに適応した。
そして社台SSのスタッフは、そのどちらの天才も敬うことを学んできた。その哲学は、2頭の象徴的存在にとどまらない。
ディープインパクトの息子、コントレイルは完璧な姿勢で歩く。まるで自分がどう見えているかを自覚しているかのようだ。三輪氏はコントレイルを「モデルのような」と表現する。
だが、その優雅さの裏に、コントレイルは父よりも熱量があり、火花がある。優等生ではあるが、積極的な優等生で、先生が質問を言い終える前に手を挙げるタイプだ。
一方のエピファネイアは当初、他の種牡馬たちに気にしている様子だった。それでも、彼の繊細さは欠点として扱われなかった。個別のアプローチの出発点になったのだ。徐々に慣らしていく脱感作、環境の再調整、そして彼が自分自身に落ち着けるようにする安心感、それが大事だった。
エピファネイアの母父、スペシャルウィークは他の種牡馬が通ると壁を蹴った。父のシンボリクリスエスは、砂埃が立つまで馬房の中を回った。社台SSが見たのは改善すべき問題ではなく、理解すべき血脈だった。
エフフォーリアは、他の者が馬を観察するように人を観察する。序列を試し、姿勢を読み、相手を認めるかどうかを決める。彼には、対等な存在として向き合う担当者が必要で、それ以下だと彼は序列を上ろうとする。
「この馬は人の上に立ちたがるところがあります」と三輪氏は言う。「相手が自分より下だと見れば、反抗的になったり、自分の方が上だと主張してくるところがあります」
「人を見分けて、優位に立ちたがる性格です。だから担当する人は、彼から“自分より上”だと見られる必要があります。そうでないと、うまくいきません。ただ、罰して『人間が上だ』と懲らしめたりしたくはありません」
「無理にすると反抗したり、さらに自分の方が上だと証明しようとしたりします。うちの経験豊富なスタッフはこの馬との付き合い方を分かっています。敬意を払い、『君が王様だよ』と伝え、きちんと立たせつつ、下に見られないようにする。対等な立場で接しようとしています」
三輪氏の指揮の下では、個性は矯正すべき問題ではなく、尊重すべき特性となる。


社台SSの“馬ファースト”のアプローチが最も輝くのが、キタサンブラックとその息子、イクイノックスのコンビだ。三輪氏はこの決断について、静かな誇りとともに説明する。
「実は、向かい合わせにしました。同じ厩舎の中で、ちょうど向かいに馬房があるんです」
この選択は、単に作業上の効率を重視だけではない。教育の機会を生み出した。
「すごく良い関係なんです」と三輪氏は言う。
キタサンブラックは馬房の中では自然体で落ち着いており、オンオフがハッキリしている。日々のルーティンそのものが、バランス感覚と自信の手本となる。現役上がりでパワー全開だった若い種牡馬、イクイノックスをその向かいに置くことで、父と子の毎日の対話が生まれた。
そして三輪氏の狙い通り、イクイノックスはあらゆるものを吸収し始めた。
「イクイノックスは父がやることを見て、すごく似た振る舞いをするようになりました」
最初は偶然の一致だった。それが習慣になった。
「それ以前から、すでに共通する特徴はたくさんあったんですが、行動がとにかく似ているんです」
そして最後には、もっと深いものになった。
「父が偉大な種牡馬だから、毎日父を見て学んでいる、という感じですね」

これは調教ではない。文化である。若きエリートのアスリートが、先輩の静かな手本から学ぶ、そのやり方だ。教え込まれるのではなく、近くにいることによって受け渡される知である。
三輪氏と社台SSのスタッフは、その文化の指揮者なのだ。
競走馬から種牡馬への移行は、身体の調整だけでは済まない。これまでとは全く違う仕事が求められる。
ナダルは種牡馬入りした当初、牝馬に向かう気持ちが強すぎたため、スタッフは横で一緒に駆けなければならなかった。三輪氏は当時を笑いながら思い出す。放牧地で放した瞬間、おそらく“最速ラップ”を叩き出したであろう、あの走りは今はどうなのか。
「前は馬と一緒にギャロップしないといけませんでしたが、今はほとんど常歩で歩けます」
誰かが気持ちを折ったからではない。服従を求めずに、抑制の価値を学ばせたからだ。
「ただ種牡馬に大人しくなってほしいとか、扱いやすくなってほしいとは思っていません。男らしく、そして紳士的でほしいんです」と三輪氏は説明する。
「牝馬に興味を持たせつつ、きちんと振る舞わせるのが難しい部分です。男としての自信は傷つけたくない。扱いやすい馬にしたいわけではない。でも“男”であってほしい。紳士で、とても落ち着いた存在に。これは本当に難しいことだと思います」
その違いが重要だ。従順なのか、落ち着いているのか。壊れているのか、洗練されているのか。
イクイノックスはその難しさを体現する存在だ。最初に来た頃、彼には“オフのスイッチ”が存在しなかった。手綱を離した瞬間、放牧地を爆発するようなスピードで駆け出し、三輪氏は柵にぶつかるのではないかと心配した。
だが、キタサンブラックの向かいに置いた。今ではイクイノックスは、手入れの最中にも父と同じように優雅に落ち着いて立っている。
「少しディープインパクトを思い出します」と三輪氏は言う。「周りに人がたくさんいても、落ち着いてリラックスしていられる。キタサンブラックも同じでした。まるでスターみたいです。自分が何をしているのか分かっていて、人を楽しませる術も分かっている」
何気ない観察のようでいて、そこにはすべてが表れている。三輪氏は馬を見ているだけではない。パフォーマーであり、個性であり、そして新しい職業の奇妙な要求を渡っていく個人として彼らを見ているのだ。
そして厩舎のいちばん奥にはオルフェーヴルがいる。今もまだ、学ランのボタンを留めることを拒み続けたままだ。
「もし、いつかオルフェーヴルの息子がオルフェーヴルの向かいの馬房に入ったら、たぶん仲良くできないと思います」と三輪氏は笑いながら言う。
二人の天才が近い場所にいれば、カオスが生まれる。だからオルフェーヴルは、これからもずっと自分の角にいて、自分のやり方で世界を達観しているのだ。いつまでも若く、いつまでも遊び好きで、そしていつまでも三輪氏に自分の人生を考えさせながら。
「本当に尊敬しています。人間社会、組織の中にいると、上司が何を考えているかとか、くだらないことにも気を配らないといけません。でもオルフェーヴルは、いつも自分のやりたいことをやって、いつも自分を表現しています。目の前に牝馬がいれば嬉しくなる。いつも遊んでいて、いつもやりたいことをやっている。少し羨ましいです」