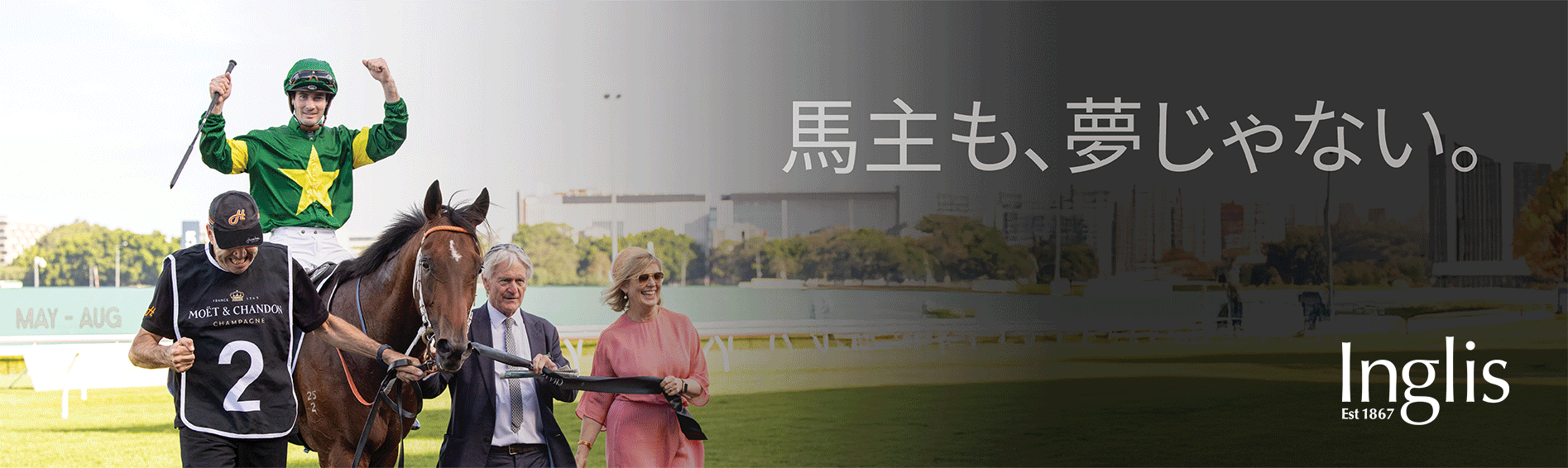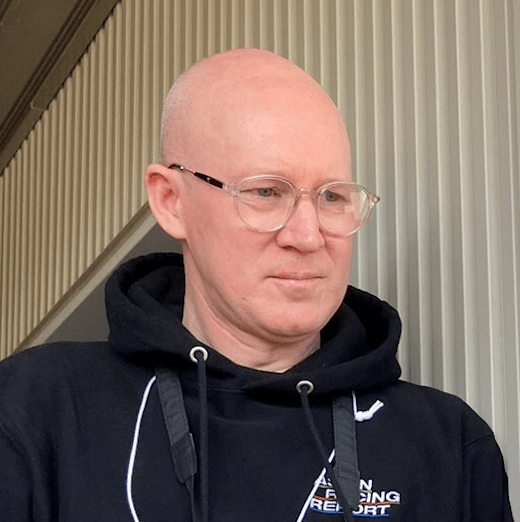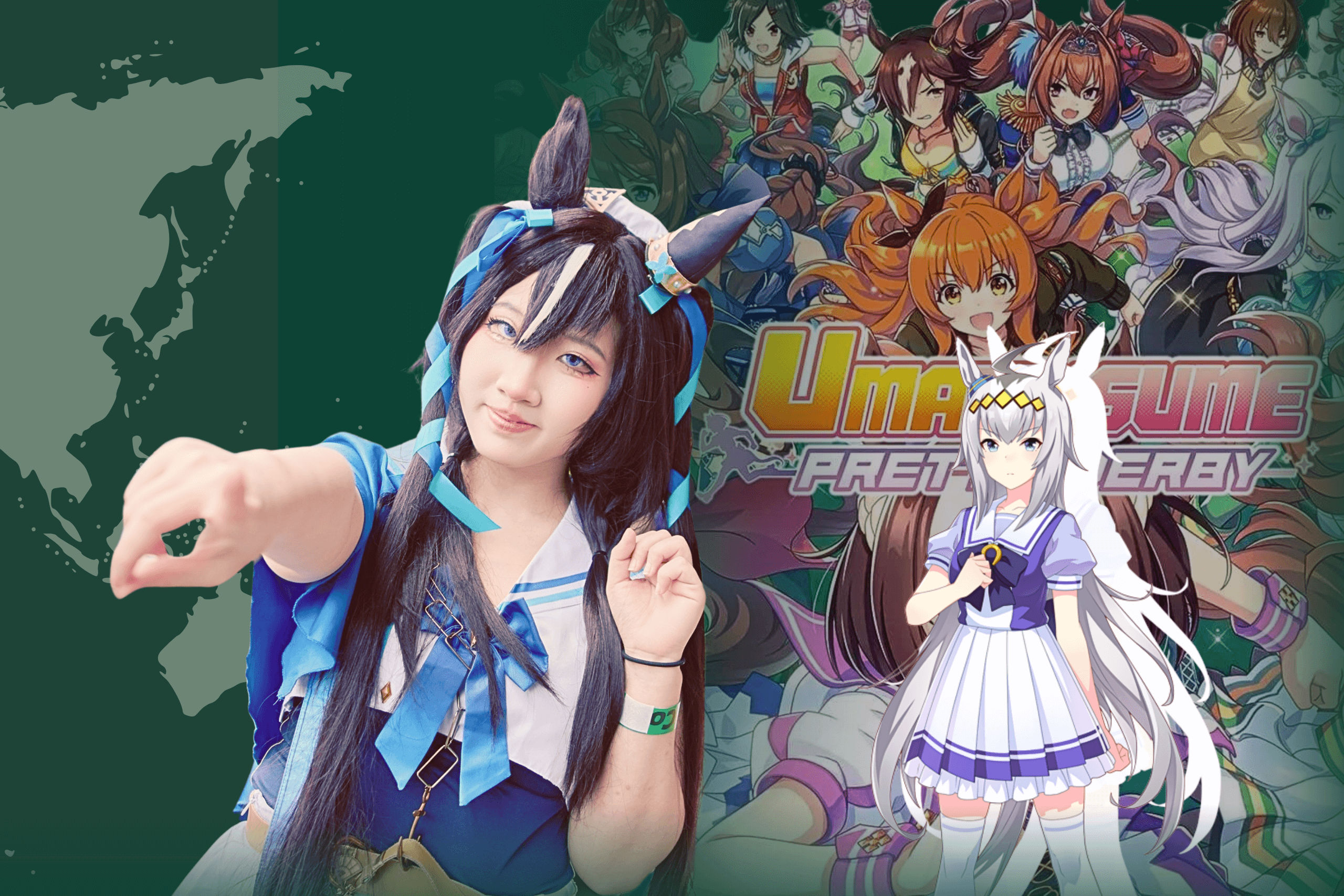ブラジル、ガベア競馬場。勝ち馬のベットユーキャンが引き上げてくると、鞍上のフランキー・デットーリ騎手は、両腕を高く掲げて天を仰いだ。
直後、その両腕は再び空へ突き上がる。代名詞となったフライングディスマウントの衝撃を55歳の膝が受け止めた。信じがたいキャリア、その最後を飾る跳躍だった。
その光景の数千フィート上、コルコバードの丘の頂で、キリスト像が街を見下ろしていた。巨大な像は、コンクリートの両手を大きく広げ、史上屈指の名手が刻んだ最後のレース勝利を、その視線の先に収めていた。
イタリア出身のデットーリは、いったんは引退を決めながら、その決断を覆し、北米を拠点に乗り続ける道を選んだ。
それから2年、南米での別れの旅の果てに、ついにキャリア最終日の開催を迎える。そしてそこに、もうひとつのクラシックレースが加わった。ブラジルの2000ギニーにあたるリオデジャネイロ州大賞で、G1通算288勝目を刻んだ。
「感情が込み上げていますが、幸せな気持ちです」とデットーリは言い、緊張していたことも認めたうえで、「最終日に勝ち馬に乗れるなんて魔法のようです」と率直な思いを語った。
そんな瞬間には、人生の苦悩は忘れられる。削ぎ落とした体重のまま生き、働き続けた歳月も、論争も、コカイン陽性も、借金も、破産も、76万5000ポンドの税金未納も。最後にひとつ、数々の偉大な勝利を締めくくるにふさわしい記憶がキャリアに刻まれる。
チャンピオンとしての彼、彼が跨った馬たち、そして人間としての圧倒的な輝きが、そこに凝縮される。
ガベアの人々は彼を迎え、送り、拍手し、その競馬への偉大な貢献を称えた。その目に映っていたのは、ただ目の前にいるヒーローだけだった。
ブラジルでのそれが日曜の出来事なら、土曜はアンドリュー・フォーチュン騎手の日だった。
リオデジャネイロから南大西洋を越えて東へ4000マイル、ケープタウンでも、58歳の南アフリカ出身ジョッキーが両腕を天へ突き上げていた。
彼にとっての節目で、救いとなる瞬間。それはG1・ケープタウンメット初制覇であり、同じく救いを求めていた6歳の騸馬、シーイットアゲインと並び立っての勝利だった。
「ただ神に感謝したかったんです」とフォーチュンはレース後のインタビューで語った。
「神に感謝したかった。ただ、こういう形でやりたかったんです。こうやって」と続けると、彼は膝をつき、見上げ、腕を広げた。「ただ一言、『ありがとう』と言いたかった。だって私は、あらゆる依存症からここまで来たんです」
「誰も私を必要としなかった。なのに私は、今こうして、この大舞台に立っているんです」
その勢いのまま、フォーチュンはうっかり不適切な言葉(Fワード)をいくつか口にしてしまった。悪気はなく、受け止める側も大ごとにはしなかったが、それでも罰金は科された。
人生の中で彼は、比喩として『膝をついた』どころではない地点まで沈んだ男だ。
依存症から這い上がり、回復は19年目に入り、いまも続いている。少し前まで、追い切りで馬に乗る仕事すら得られなかった。体重は騎乗体重より30kgも重かった。
そこから減量の戦いに勝ち、免許の再交付を勝ち取り、そして1年前、彼は戻ってきた。
シーイットアゲインは並外れた素質を持ちながら、その多くが実を結ばなかった馬でもある。気性が原因でゲートに入るのを拒み続けたからだ。だが、ジャスティン・スネイス厩舎へ転厩し、フォーチュンが普段の調教でもレースでも手綱を取るようになったことが、必要だった変化になった。
「運命のような物語です」とフォーチュンは言った。「言いたいこと、わかりますよね?」
そう、誰もがわかっていた。フォーチュンはその日、ダブルグランドスラムでG1・マジョルカステークスも勝っていた。それでも、ケープタウンメットには何か、摂理を思わせるものがあった。
序盤からそう感じられ、残り2ハロン標でシーイットアゲインがリーガルカウンセルに並びかけた瞬間、それは確信へ変わる。相手の鞍上は、よりにもよって実の息子、アルド・ドメイヤー騎手だった。
父と子は一騎討ちとなり、最後の100mでシーイットアゲインが抜け出した。
「この馬の名前がシーイットアゲイン(もう一度見る)というのも、すごいですよね」とフォーチュン。「私は戻ってきて、また戻ってきている。馬の名はシーイットアゲイン。そして私は、またやって、またやっているんです」

フォーチュンにとってシーイットアゲインという名が予兆を帯びていたなら、翌日のデットーリにとっては、ベットユーキャン(君ならできるよ)という名もまたそうだった。
ベットユーキャンは16頭立ての単勝オッズ15倍の伏兵で、多くの人が勝つ可能性を低く見ていたことを示していた。
ジョアン・モレイラ騎手はIdol Horseの取材に、「伏兵で勝つところを見られたのは本当に素晴らしかったです」と目の当たりにした感想を話す。
「あれだけ楽しんでいる姿を見ると、こちらも嬉しくなりました。みんなが興奮していましたし、あそこで起きたことは、きっと永遠に彼の心に残るはずです。私たちは、彼がこの競馬というスポーツのためにしてきたことに、どれほど感謝しているかを示せたのですから」
世界各地で生ける伝説と対戦してきたブラジルの名手にとって、デットーリがブラジルで騎乗したことは胸が躍る出来事だった。
だが、宇宙の因果でも、ただの偶然でも、見方はどうあれ、フォーチュンに起きたのと同じように、デットーリにも流れが寄り添っていた。そのときモレイラは一歩下がって見守るしかない。ベットユーキャンが、単勝オッズ9倍のオレゴンムーンを置き去りにしていったからだ。
「ベットユーキャンが良い馬なのはわかっていましたが、私の評価ではトップ5に入れていなくて、6番手でした」とモレイラは続けた。「でもフランキーなら、ああいう一発をやってのける。彼は本当に素晴らしい騎手ですから」
42歳のモレイラは、デットーリから影響を受けてきた世界中の騎手のひとりでもある。クリチバ出身の彼にとって、その始まりはサンパウロの騎手学校に入ったときだった。
壁に貼られていたのはデットーリのポスターで、彼が初めて見た『世界的なジョッキー』でもあった。ゴドルフィン全盛期、その頂点の写真と、デットーリが跨ってきた名馬たちの姿だ。
「フランキーは、ずっと私の一番の憧れでした。騎乗スタイルも能力も見てきました。若い頃の彼はとても運動能力が高く、間違いなく私たち若手の刺激になりました」とモレイラは言う。
「彼と同じことをやりたかった。でも当時の私にはできなかった。だから一つひとつ積み上げて、改善し続けるしかなかったんです。それでも、駆け出しの頃に、ドバイミレニアムやドバウィのような馬で勝つ彼を見ていたことは、はっきり覚えています」
「私たちはいつも彼の騎乗を見ていました。強い馬に乗り、強い騎手たちを相手に戦うと分かっていましたし、ああいうレースを見るのが好きだったんです」
その文脈があって、モレイラは、デットーリがリオの2000ギニーを勝ったことは「非現実的」だとしつつ、ガベアの癖を知り尽くした騎手たちを相手に、技術と馬術が形になったことを喜んだ。彼が「本当に良い騎乗」だと捉えた勝利でもあった。
「リオの騎手は、少し攻撃的で、急かして、そのまま行ってしまうところがあります」とモレイラは傾向を説明する。
「私の理解では、この馬はスタートが良くて、いい位置を取れるのですが、そのあとのレースの中盤、三分の二の区間で一度息を入れないと、最後まで脚が持たない。これまで彼らは、そこを間違えていたんです。でもフランキーは正しくやった。きちんと息を入れさせました」
「それに、この馬は人気上位3頭か4頭に入っていなかったので、他の騎手は意識しませんでした。気づいたときには遅かった。誰も気にしていないうちに、彼がそこにいて、そしてもう勝っていたんです」
モレイラは、デットーリの存在をブラジルの伝説的サッカー選手、ペレになぞらえる。
自身の騎手人生の中で彼と同時代にいたこと、そして歴史上誰よりも多く勝ったとされるもう一人のブラジルの偉大なジョッキー、ジョルジ・リカルド騎手とも同じ時代を走ってきたことを、栄誉として語った。
「私はとても恵まれていました。フランキーとジョルジ、2人のそばにいられたんです」
「この前にも騎手はいましたし、この先にも騎手は出てきます。でもこの2人の偉大な騎手を見て、そして彼らと競り合って乗る機会は、もう持てないでしょう。私は2人とも相手にして乗るという喜びを味わえました」
「ペレと一緒にプレーしたと言う人がいるみたいなものです。いまはメッシがプレーしていて、彼と一緒にプレーしている選手は、その感覚を語れます。でもペレと一緒にプレーするとはどういうことか、それは語れない。ジョルジとフランキー、両方と競り合って乗るというのはそれと同じです」
「彼らもまた現れては去っていく。フランキーは引退して去り、ジョルジも去るでしょう。そして私も去っていく。それが人生です」
フォーチュンはまだ去っていない。だが年齢を考えれば、本当の引退がそう遠くないのも確かで、土曜の勝利が最後のケープタウンメットになった可能性すらある。
彼もまた稀有な才能であり、デットーリと同じく名手だ。ただし、その人生の道筋は、イタリア人が享受し、ときに背負ってきた世界的名声へと運命づけられてはいなかった。
それでも、2人の男が、これほどのタイミングで、1日違いで、勝利を味わう。2つの驚くべき日々の連なりは、神の摂理という感覚に、いっそうの説得力を与える。唯一無二の2人。苦難と勝利をそれぞれ背負い、馬上でそれぞれの天才を授けられた者たち。そして個人的な意味を持つ勝利に祝福された者たち。
巨大なキリスト像がデットーリを見下ろしたように、フォーチュンは天を仰ぎ、両手を口元に当て、歓喜のキスを空へ投げた。
「神に捧げます」彼はそう言い残した。