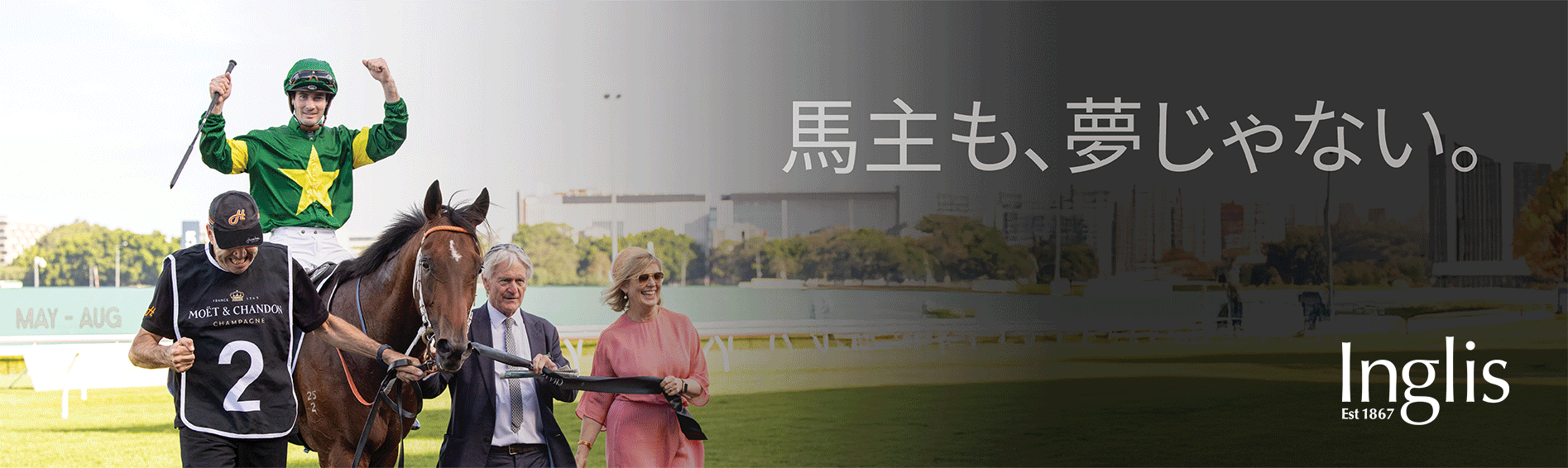日曜日に行われたG1・凱旋門賞の結果は、12月の香港国際競走に直接的な影響を及ぼすものではないかもしれない。昨年の香港ヴァーズを制し、理想よりも柔らかい馬場で粘り強く4着に入ったジアヴェロットが、再び主役の一頭として戻ってくる可能性が高い。
しかし、凱旋門賞馬となったダリズの血統が、香港競馬の祭典に新たな歴史を刻んだことは間違いない。
香港ジョッキークラブのウインフリート・エンゲルブレヒト=ブレスゲスCEOは以前から、香港国際競走を「繁殖価値に影響を与える真の年末総決算」とする構想を長年掲げてきた。課題は、生産者に「シャティンでの勝利が血統的価値を高める」と理解してもらうことだった。
「繁殖価値を高めることこそが、私たちに残された成長余地です。ただし、その進歩が一度に大きく進むことはないでしょう」と彼は2016年に語っている。
そして、その「段階的な」進歩は日曜日に大きく前進した。香港国際競走の歴史に深く根ざした血統、そこから誕生した3歳馬のダリズが、凱旋門賞を制したのである。
アガ・カーン殿下の自家生産馬であるダリズの父は、3歳時で凱旋門賞を制して現役を引退したシーザスターズ。その母、アーバンシーは1993年4月に行われた香港カップに出走し、ロマネコンティ(のちのコーフィールドカップ、メルボルンカップ覇者となるエセリアルの母)の6着に敗れている。このアーバンシーこそが、香港とこの血統を繋ぐ最初の存在となった。
シーザスターズは今年の凱旋門賞で3着に入ったソジーの父でもあり、アーバンシーの孫であるフランケルは2着馬・ミニーホークの父でもある。過去10年の凱旋門賞勝ち馬のうち、8頭がアーバンシーの直系子孫にあたり、もう1頭のトルカータータッソも父母両系でアーバンシーと近い血統にある。
この血統背景だけでもダリズと香港の関係は明白だが、その母系がこの絆を決定的なものにしている。
ダリズの母は、2009年の香港ヴァーズを制したダリヤカナであり、彼はその7番仔にあたる。ダリヤカナの産駒は7頭中の6頭がリステッド以上の勝ち馬(ステークス勝ち馬)となり、その中には2015年の香港ヴァーズ3着、G1・ガネー賞勝ち馬ダリアンも含まれる。だが、ダリズこそが彼女の真の傑作だった。

これは、現役時代に香港国際競走で勝利を挙げた繁殖牝馬の仔としては史上最高の成績だ。シャティン競馬場での実績が、世界の血統形成に影響を及ぼし得ることを証明した。
香港国際競走の歴史を振り返ると、これまで14頭の牝馬が主要レースを制している。そのうち、11頭は1989年から2010年の間に集中している。
2010年以前の勝ち馬のうち、グレイインヴェイダー、ロマネコンティ、ウィジャボード、ダリヤカナの4頭がG1勝ち馬の母となり、ボルジアはG1勝ち馬の祖母となった。さらに、プライド(息子のワンフットインヘヴンが2016年香港ヴァーズで3着)など、4頭がステークス勝ち馬を輩出している。
名牝と謳われるサンラインや小柄な馬体で名を馳せたヴァレーアンシャンテは、その輝きを次代に伝えることはできなかったものの、その記録は今も健在だ。
一方、香港国際競走から輩出された種牡馬は数こそ少ないが、特に日本で大きな影響力を持つようになっている。
サトノクラウン(香港ヴァーズ)、アドマイヤマーズ(香港マイル)、ロードカナロア(香港スプリント連覇)はいずれも2025年、世界各地でG1勝ち馬を送り出した。また、アクラメーション、ランカスターボンバー、レッドウッド、タワーオブロンドンといった敗れた馬たちもG1馬を出しており、QE2世Cを優勝したルーラーシップを始め、ウェルキンゲトリクス、トレジャービーチらも同様の成功を収めている。
これまで、香港国際競走のレースを制した牡馬は計40頭。うち11頭がG1勝ち馬を輩出(障害G1馬を含めると13頭)、6頭がG2勝ち馬の父となり、さらに2頭がステークス勝ち馬を出している。
グローリーヴェイズ、モーグル、ダノンスマッシュといった近年の勝ち馬はまだ種牡馬キャリア初期にあり、またドミナントやイーグルマウンテンなどは種付け頭数が限られていたことを考えると、この成功率はきわめて有望といえる。
そして、ダリズの凱旋門賞制覇は、アーバンシーが香港に遠征した30年以上前から始まった歴史を見事に完結させた。
香港ジョッキークラブにとって、香港国際競走が単なる年末のフィナーレではなく、サラブレッドの血統という世界的な物語の中で、確かな礎石となり得ることを示す歴史的勝利だった。