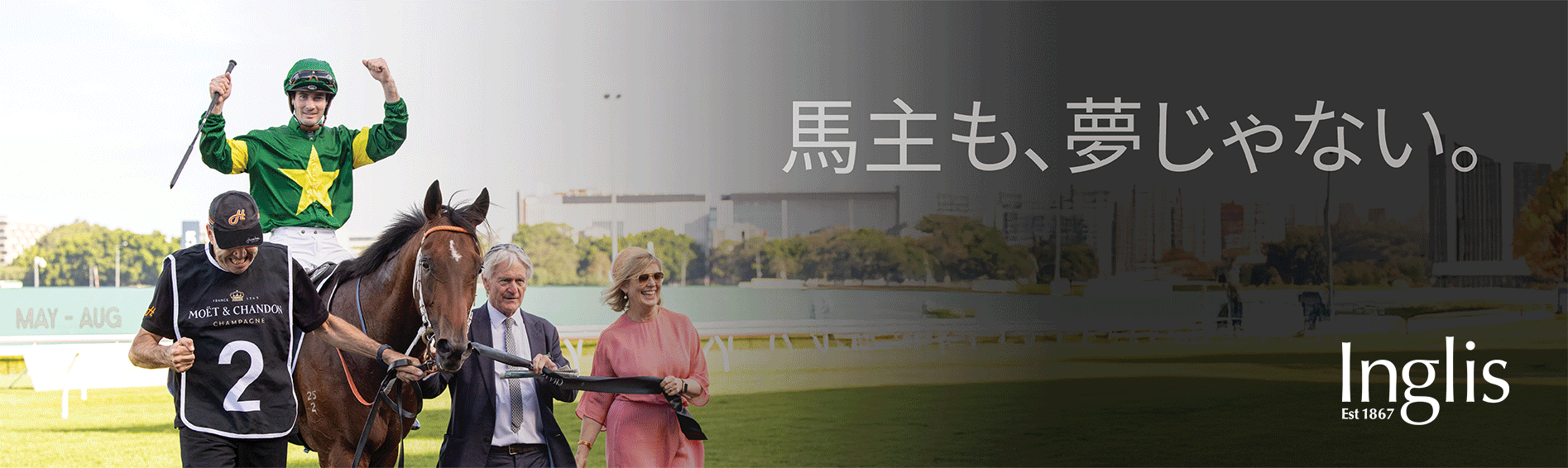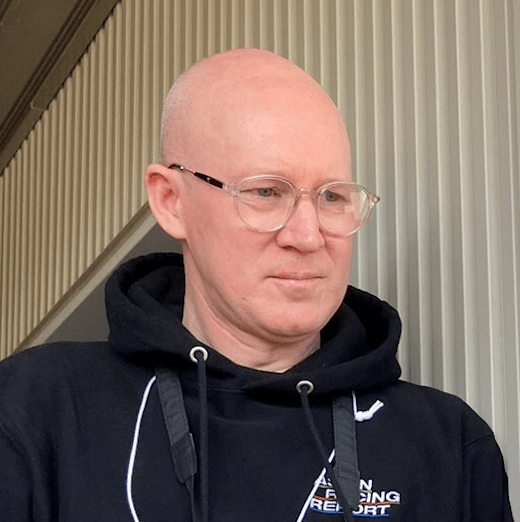発走前、ロンシャン競馬場には「盛り上がっていこう!」というアナウンスが響き続けた。観客席からは中途半端な歓声が上がったが、そんな必要はなかった。スポーツファンは心得ている。ゲートが開いて17頭がヨーロッパ最高賞金のレースに飛び出すと、自然発生的な大歓声がブローニュの森を越えて響き渡った。
馬群が直線に向くと、再び大地を揺るがすような声が上がった。スタンドも芝生席もぎっしりと埋め尽くされ、クールモアのミニーホークがスパートをかけると歓声がひときわ大きくなる。アガカーンスタッドのダリズが迫ると、すべてのファンが声援を重ね、そしてその牡馬が最後の一完歩で勝利をもぎ取ると、耳をつんざくような叫びが競馬場を包んだ。
アタマ差の勝利。ミカエル・バルザローナ騎手とフランシス=アンリ・グラファール調教師に、初の凱旋門賞制覇をもたらした瞬間だった。
「このレースは、本当に胸に響く特別なものです」と、グラファール師は語った。
「少年のころからこのレースに憧れてきました。いつかこの勝負服で勝ちたいと夢見ていたんです」
緑地に赤い肩章。アガカーンスタッドの勝負服が凱旋門賞で手にした勝利はこれで5度目。しかも今年2月にアガ・カーン殿下が逝去して以降、初の戴冠でもあり、格別の意味を持つ勝利だった。
故アガ・カーン殿下の娘、ザーラ王女の隣に座ったバルザローナ騎手はこう語った。
「これこそが、私たちがこの仕事をする理由です。この勝負服を着れば、いつでも偉業が可能だと分かっていました。偉大な騎手たちの足跡をたどることができて、本当に幸運です」
そして、短く「ついにやり遂げました」と、締めくくった。
だが、日本競馬界にとってはまだ終わっていない。
日本のホースマンと熱心なファン、ロンシャンに駆けつけた人々も、深夜の東京競馬場でパブリックビューイングを見守った人々も、そして自宅で観戦したファンも、どれほどこの勝利を待ち続けているだろうか。
エルコンドルパサーがモンジューに差され、2着に敗れた1999年から、すでに26年の月日が過ぎている。
「応援してくださった皆さんに、結果を出せず本当に申し訳なく思います」クロワデュノールに騎乗した北村友一騎手は、毅然とした表情のまま、瞳に悔しさをにじませながら語った。
クロワデュノール、ビザンチンドリーム、アロヒアリイ、この3頭もまた、勝利を逃した35頭の日本馬に名を連ねた。そこには、惜敗したディープインパクト、ナカヤマフェスタ、オルフェーヴルといった名も刻まれている。
1999年のエルコンドルパサーの2着、日本が世界の頂に迫ったあの走りの記憶はいまも消えない。
北村騎手はレース前、希望に満ちた数時間の中で、Idol Horseにこう語っていた。
「その時まだ小さかったので。当時は13歳。あの時は本当にただただ2着でもすごいなと思って観ていました」
「今日は僕が勝ちます。外枠は難しいですけど頑張ります」
日本の陣営には確かな自信があったが、それは同時に歴史の重みを知る現実的なものでもあった。日本馬関係者のひとりはこう漏らした。
「このレースに関しては、誰も自信満々にはなれませんよ」
一方、スタンドの階段や芝生席では、あらゆる年代の日本のファンが、ヒーローたちの勝負服の色をあしらった応援旗やグッズを掲げ、レース前から明るい表情を見せていた。
きっと、ロンシャンを照らした朝の陽光に後押しされてのことだろう。その後、空は気まぐれに雲が広がったり、淡い陽が差したりを繰り返し、そしてレースが行われている最中には雨が降り、コースの上に虹がかかった。
京都から来たタケウチアキオさんは語る。エルコンドルパサーが2着だったとき「20歳くらい」だったという。
「サンクルーでは本当にいい走りをしていたので、勝つと思っていました。だから少しがっかりしましたね」と振り返る。

それでも、タケウチさんは4年後に再びパリを訪れ、日本馬不在の中、アガ・カーン殿下のダラカニが制した2003年の凱旋門賞を現地で観戦した。それ以来、2024年、そして今年と2年連続で現地観戦を果たしている。
「3週間前にはプランスドランジュ賞を見に来ました。クロワデュノールは本調子ではなかったけれど、悪くありませんでした。今回はもっと良いと思っています」
同行していたのは東京出身でミュンヘン在住のハヤシコウイチさん。「僕たちは意見が分かれています」とタケウチさんは笑い、ハヤシさんはこう続けた。
「ミュンヘン競馬場でオイシン・マーフィー騎手に会って、一緒に写真を撮ったんです。とても親切な方でした。それ以来、ずっと応援しています」
彼らの背後では、えんじ色の凱旋門賞スタッフシャツを着たダンサーたちが、スタンド前で音楽に合わせて踊っていたが、その光景はどこか場違いに映った。フランスの若者はそれを求めているのかもしれないが、日本の若者たちは、その派手な演出よりも馬そのものを見つめていた。
日の丸を掲げた若い3人組のうち、アンドウヒロアキさんは和装姿で、友人のオオウチヒカルさんはアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』のゴールドシップのぬいぐるみを抱えていた。
「最初はウマ娘をきっかけに興味を持って、そこから競馬を追うようになりました」とオオウチさん。
2人はYouTubeで過去の名馬の映像を見て、凱旋門賞の歴史を学んだという。ゲームや物語、ヒーロー、そしてレースの興奮、それらが彼らを競馬に惹きつけた。
「アニメがとても印象的で、実際の競馬場であの雰囲気を肌で感じたくなったんです。行ってみたら最高でした。東京の安田記念でロマンチックウォリアーが勝つのを見ました。香港のファンの声援がものすごくて驚きました」と、アンドウさんは語る。
別の若者、東京出身のイナダシュウさんは、オーストラリアのアスフォーラがG1・アベイドロンシャン賞を制したとき、ロンシャンのゴール板のすぐ先で観戦していた。
ドウデュースのキャップにビザンチンドリームの応援フラッグを手にしていた。競馬を本格的に見るようになったのはわずか2年前だというが、日本の凱旋門賞の歴史はすべて予習済みだという。
「同僚に誘われて東京のG2・フローラステークスを見に行ったのが最初でした。馬券じゃなくて、レースそのものが面白くて。スポーツとして本当にワクワクしました」
そして、少し照れながら言った。
「オルフェーヴルが好きだったので、子どものころから凱旋門賞は見ていました。もし日本馬が勝ったら……泣いてしまうと思います」


だがこの日のロンシャンで流れた涙は、歓喜のそれではなかった。またしても、日本から来た精鋭たちが真価を示すことなく散った年になった。
ビザンチンドリーム、クロワデュノール、アロヒアリイの3頭は、それぞれフランスで前哨戦を制して臨んだが、結果は5着、14着、16着。日本の騎手・調教師・記者の表情には深い失望がにじんだ。
ビザンチンドリームの坂口智康調教師は、それでも「このクラスと距離で力を示せたことは収穫」と語った。
一方、アロヒアリイの田中博康調教師は、険しい表情で検量室を後にし、当初は「ノーコメント」とだけ残した。しかし、やがてカメラの前に立ち、ファンへ感謝を述べた。
「正直に言えば、このレースは本当に簡単ではありません。決して軽視していたわけではありませんが、馬場コンディションだけでなく、この環境そのものへの適応が必要だと痛感しました」
北村騎手とクロワデュノールの斎藤崇史調教師もまた、重馬場を言い訳にはしなかった。
「馬場は関係なかったと思います」と北村騎手。むしろ、外枠と前に馬を置けずに先行したことが馬を落ち着かせなかったと振り返る。
クロワデュノールは、最初の1400mを1分27秒93という近年では2番目に速いペースで先行した。
「(事前の作戦では)先行がどうという話ではなかったのですが、思っていたより悪い方の展開になってしまったなとは思います」と斎藤師。
「今回は残念だったのですが、これが全てではないと思うので、もう一度日本で走れるところを見せて、来年チャンスがあればまた来られたらいいと思いますが、そこは馬のことですし、オーナーもいることなので、まずは日本に持ち帰って、もう一度きちんとした状態で競馬を使うところから始めたいと思います」
一方、アロヒアリイのクリストフ・ルメール騎手は、馬場の影響を挙げた。
「馬場がかなり重くて、脚に切れがなかった。加速できなかったんです。日本馬はこういう馬場に慣れていません。今日は残念でしたが、日本に戻ればトップレベルで戦えると思います」


ルメールもまた、日本勢と同じく初の凱旋門賞制覇を逃した。46歳、夢を追う時間が限られていることを思えば、この敗北の痛みは深い。
取材を終えてファンとの写真に応じていたルメール騎手の視線が、ふと上を向いた。通路の上に立つ小さな日本の少年が、ルメールの顔写真を切り抜いたパネルを手に振っていた。
ルメールは笑顔でその少年に手を振り返した。その光景は、競馬の未来を映すようだった。英雄たちに憧れ、このスポーツの喜びと悲しみのドラマに心を奪われた、かつてのグラファール師のような、夢を抱くひとりの少年の姿だった。