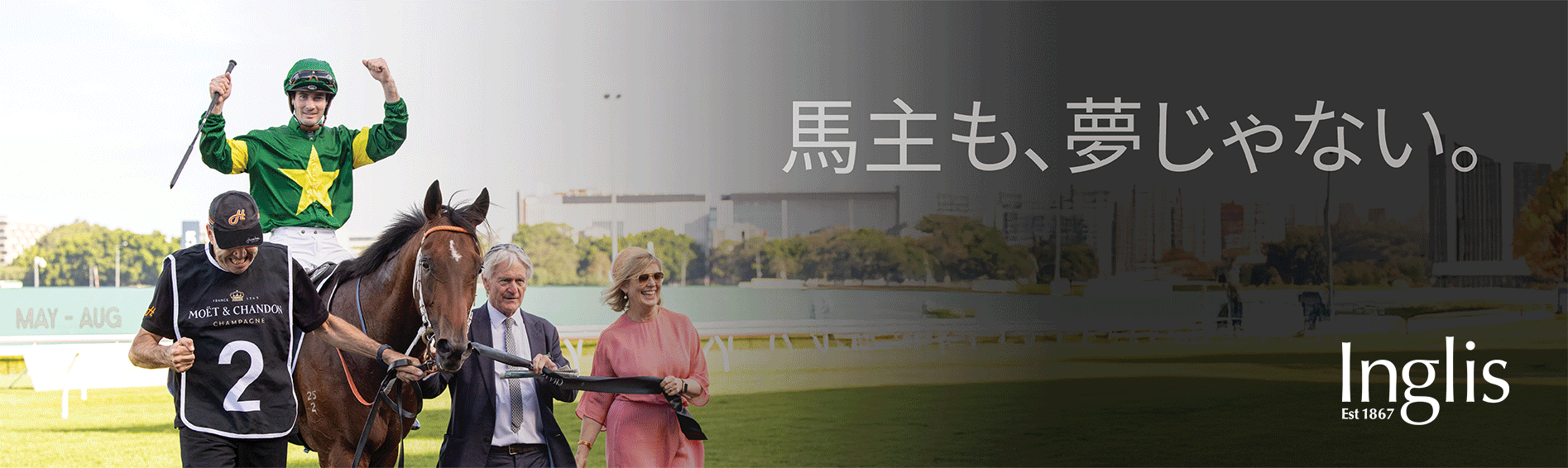「自信を失えば…」シドニーNo. 1の新星、ザック・ロイド騎手が見つけた “攻守の境界線”
シドニーの天才ジョッキー、ザック・ロイド騎手はかつて、勝利のたびに裁決室に呼ばれるような荒削りな才能だった。しかし、それを克服して成長した今、チャンピオンへの道を駆け上がろうとしている。
騎手たちの間には暗黙のルールがある。そこまで厳格ではないにせよ、少なくとも「何を言うべきで、何を言わざるべきか」は空気を読む、そんな不文律だ。競馬界の“警察”である裁決委員が呼び出してきたときにこそ、それは試される。
よくあるのはこうだ。騎手Aが呼ばれ、レース中明らかに騎手Bが非を犯した件について説明を求められる。裁決委員たちは映像を流し、スローにし、角度を変え、細かく突っ込んで質問する。要は「あの騎手が悪い」と言わせたいのだ。だが、多くの場合、証言者は決定的な一言を口にしない。「お互い様だ、持ちつ持たれつ」それがこの世界の慣例である。
だからこそ、もしある騎手が不利になるような発言を口にしたとき、裁決委員は背筋を正し、記者は耳をそばだて、周囲は思うのだ。「これは相当悪質なケースだったのだな」と。
そんな “不文律” がほんの少し曲げられたのは、真冬のシドニー、注目度の低い土曜開催だった。熱心なファンですら心拍数を上げるような舞台ではなかったが、その日、小さな出来事が波紋を広げた。
荒削りな宝石
当時、ザック・ロイドはシドニーの見習騎手リーディング。その日すでに2勝を挙げていたロイドは、若手騎手にとって一つの到達点、つまりはシドニーで減量特典を使い切り、“一人前” として認められる存在になろうとしていた。もし彼が箒にまたがっていても、ファンはこぞって馬券を買っただろう。
そして次のレースで、ロイドは王者に挑んだ。相手はシドニーの絶対的チャンピオン、ジェームズ・マクドナルド騎手だ。
“勝負欲” を漲らせた騎手は危険であり、ロイドはまさにその状態だった。マクドナルドが騎乗したユナイテッドネイションズが失速し始めたとき、ロイドはすぐ背後でチャンスをうかがっていた。彼の相棒は、名門クリス・ウォーラー厩舎が擁する古豪のカーケビー。ウォーラーはマクドナルド最大の後援者でもある。
ローズヒルの直線を回ると、ロイドの馬がマクドナルドの遅れる馬を交わすのは時間の問題だった。そこで選択を迫られる。外に持ち出して安全に抜けるか。数完歩だけ我慢し、その後で進路を切るか。それでは先頭を捕らえるには遅すぎるのか。
それとも、ほんのわずかに内へ舵を切り、マクドナルドの内側に開きかけた狭い隙間へ滑り込むのか。
ロイドの師匠であり、豪州史上屈指の名手にして殿堂入り騎手のダレン・ビードマン氏は、近くのテレビに釘付けになっていた。自分の弟子がどんな判断を下すか、固唾をのんで見守っていた。
ロイドはマクドナルドを力で押しのけようとする。馬同士がぶつかり合う様子は目を覆いたくなるほドの光景だ。見ている者の心臓を一瞬で喉元まで跳ね上がらせた。両馬の頭は揺れ、額をぶつけ合いながら、まるでリングで間合いを詰め合うボクサーのようだった。
マクドナルドは当初、ロイドをポケットに閉じ込めようとしたが、事態の深刻さを悟り、ぶつかり合いを続けることは誰の利益にもならないと判断。進路を開け、ロイドを抜け出させた。
「取り返しのつかない事態になっていた可能性もあります」
マクドナルドはレース直後、裁決委員にそう告げた。騎手の “不文律” を越えた発言だった。結果、ロイドはまたもや騎乗停止処分を受ける。1年余りの短期間で11度目の処分、常習犯中の常習犯だった。
「彼はイン側から機を伺っていて、あと30メートル待てばよかっただけなんです。老練な雄牛と若い雄牛の戦いですよ。まだ首ひとつ分後ろにいながら、肩で押しのけようとしたでしょう。あれは傲慢か愚かさか、そのどちらかです」とビードマンは振り返る。
だが、トップに立つ騎手にとって、傲慢さは不可欠なのではないだろうか。時には「自分は他より上だ」という心構えだ。「傲慢と自信の間は紙一重です」とビードマンは続ける。
「自信が行き過ぎれば、それは傲慢となり、何でもできると錯覚してしまいます。だが、一瞬の判断で『できる』と信じて動くには、ある程度の傲慢さも不可欠です。頂点に立つにはほんの少しの傲慢さが必要です。ただし、その境界をどこまで踏み込めるかを理解していなければなりません」

オーストラリア競馬において、ロイドほどの逸材が現れたのは、それこそビードマン以来と言っても過言ではないだろう。
元騎手のビードマンは現役時代に香港でも腕を振るい、ジョン・ムーア調教師に初のリーディングタイトルをもたらした。しかし、衝撃的な落馬事故により、そのキャリアは突然の終わりを迎えた。
さて、話を戻そう。ドバイのモハメド殿下が率いる世界的な名門、ゴドルフィン・オーストラリアで10代のうちから見習い騎手として抜擢される若手騎手など、果たしてどれほどいるだろうか。
ロイドには独特の存在感がある。礼儀正しく、飾らない一方で、立ち居振る舞いは堂々としており、何より頭が切れる。高校の卒業試験では85点を記録したという。自信家でありながら思慮深く、そこに少しの “ショーマンシップ” が垣間見えるのも彼の特徴だ。
1980年代、キングストンタウンのコックスプレート3連覇のうち2回を騎乗停止で逃した男、稀代の天才 “ミラクル” ことマルコム・ジョンストン元騎手もかつてはそうだった。ロイドの才能は、彼を大舞台に押し上げたその型破りな才能と似たものがある。
「自信」の裏付け
シドニーから南へ車を走らせること90分、木曜開催が行われていたケンブラグランジ競馬場で、ロイドは騎乗の合間にIdol Horseの取材に応じてくれた。
ロイドにとってはごく普通の一日だっただろう。彼は、白いシャツ姿で、髪にはブロンドのハイライトを入れていた。国際的な環境で育った彼の英語には独特の訛りが混じる。次の騎乗まで数時間あったため、裁決委員の許可を得て、短い昼食に向かう直前だった。
ショーマンシップや自信という話題になると、彼は少し照れくさそうに笑う。きっかけは昨年のジ・エベレストを前に、競馬ニュースサイト『Racenet』が撮影した短い動画だった。その中でロイドは冗談半分とはいえ、こう言い放った。
「ステフィマグネティカはこのレースで一番強い馬で、僕はこのレースで一番の騎手。だから勝てると思います」
ジ・エベレストは総賞金2,000万豪ドルを誇る豪州スプリントの祭典。マクドナルド、クレイグ・ウィリアムズ、ナッシュ・ローウィラー、マーク・ザーラ、レイチェル・キングら歴戦の名騎手が顔を揃える舞台である。
「言ったのは事実です」とロイドはニヤリと笑う。「ちょっと生意気すぎましたし、かなり大胆でしたね」
だが、それは必ずしも間違いと言えるのだろうか。
「自信を持たなきゃ……この世界ではそれが命取りになりかねません」と彼はトラックを見やりながら語り始める。「もし誰かが自分より強い自信を持っていたら、その時点で勝負は負けたも同然です。そんな状況は絶対に許されません」
「自分を疑うくらいなら、最初からゲートに向かわない方がいい。ザック・パートンだったり、ジェームズ・マクドナルドを見てください。みんな自分自身を世界最高の騎手だと信じているはずです。そうでなければ、世界の頂点には立てません。その心構えは自分も取り入れようとしています」
ロイドの急成長ぶりが人々を惹きつけるのも当然だろう。彼が初めて騎乗したのはおよそ5年前、クイーンズランド州のダルビー競馬場でのこと。1.3倍の断然人気馬だったサティーンに跨がった。見習いのデビュー戦では、調教師が勝ちやすいレースを用意するのが通例で、当時彼の師匠だったトビー&トレント・エドモンズ父子も例外ではなかった。
そのレースで、ザックの兄ジェイデンは2番人気馬に騎乗し、序盤から弟の馬の外に張り付き、終始プレッシャーをかけ続けた。
「直線残り400mで『じゃあな!』って言ったんです」とザックは笑う。時速70km近いスピードで駆けるデビュー戦で、しかも相手が兄とはいえ、並走する騎手に冗談を飛ばす。その胆力はただものではない。
「そしたら僕の馬が一気に伸びたんです。本当に爽快でした」
父ジェフは当時の光景について、「勝ってくれてよかったですよ。2人を車で家まで送らなければならなかったからね。もし負けていたら、ザックはジェイデンを責めていたでしょう」と振り返る。
その日の最終騎乗、ロイドは2.3倍の人気馬でゲートを出た直後、落馬した。デビューの一日は、競馬に常に付きまとう『天国と地獄』が凝縮されていた。
しかし、クイーンズランド州で勝ち星を量産する少年に、豪州全土の視線が集まるのは時間の問題だった。ロイドはやがてシドニーへと拠点を移し、当時ゴドルフィンの専属調教師を務めていたジェームズ・カミングス師の厩舎に加わった。そのカミングスを支えていたのが後の師匠、ビードマンだった。
勝利は瞬く間に積み重なった。ゴドルフィンの後押しと、まるで ”チート” のような減量特典を武器に、ロイドは瞬く間に頭角を現し、見習い騎手リーディングを2年連続で獲得。21世紀以降にこれを達成したのは3人目、サム・クリッパートン騎手(2012/13年、2013/14年)、ロビー・ドーラン騎手(2018/19年、2019/20年)に続く大記録だった。
2022/23年シーズンには76勝を挙げ、シドニーにおける年間の見習い騎手勝利数としては、40年以上前のウェイン・ハリス騎手以来となる記録を打ち立てた。
さらにその活躍は、シーズンを通じてシドニーで最も優れた競馬関係者に贈られる『バート・カミングス・メダル』につながった。2010/11年以降、この栄誉はクリス・ウォーラー調教師がほぼ独占してきたものだ。ロイドは記録を塗り替えるだけではなく、検量室のベテラン勢をも刺激する存在となった。
「検量室では僕が誰よりも若く、新しい世代の空気を持ち込んでいます」とロイドは語る。
「それがプラスに働くこともあれば、反感を買うこともあります。特に年上の騎手たちは慣れていないでしょうね。僕の育ち方は彼らとは違います。もっとオープンで、ファンと触れ合うのが好きなんです。声をかけてもらえると本当にうれしいですね」
ロイドを語るとき、シドニー移籍直後に何度も裁決室に呼び出された過去を避けて通ることはできない。隔週で呼ばれていたようだったと問われると、彼は「毎日呼ばれていた気がします」と笑って答えた。
「振り返れば、当時は自分が邪険に扱われていると思っていました。評判が立てばその分だけ厳しく見られるものですし、実際に僕自身もアグレッシブでしたから」
「それでも後悔はありません。シドニーで自分の実力を証明したくて、勝負にこだわったからこそ、高みに手が届いたと思っています。あの時の積極的な騎乗がなければ勝てなかった馬もいたはずです」
「今は本当に努力していますし、今季は裁決室に呼ばれることなくやれています。あの境界線はまさに紙一重です」
その成長を導いてきた存在、それがビードマンだった。
ロイドには一時、集中力を欠く兆しが見え始めていた。大きな問題ではなかったが、調教を少し早めに切り上げたり、準備に身が入らなくなったり、あるいは騎乗停止を気にしすぎたりしていた。そんなとき、ビードマンがよく口にするフレーズがある。
『己の姿勢で限界が決まる』
ある日、彼はロイドを脇に呼び寄せ、もう一つの言葉を贈った。
『いいかよく聞け、鉄は鉄によって研がれるんだ』
ロイドは苦笑いを浮かべて振り返る。「まず最初に『どういう意味ですか?』って聞いたんです。すると『努力すれば結果がついてくる』と言われて。確かにその通りでした。騎乗を重ねるほど、本番の自分はどんどん研ぎ澄まされていきます」
もう一人の師匠、父ジェフ
競馬一家に生まれた者は、生涯を馬と共に過ごすことが宿命のように思われる。だがロイドの場合、その才能は休む間もなく動き続けた “パスポート” と共に磨かれていった。
父のジェフ・ロイド元騎手は現役時代、母国の南アフリカを中心に、香港、モーリシャス、オーストラリアでも活躍した世界的な名ジョッキーだった。

6歳のザックは、家のソファを馬に見立てて跨がり、父が香港の名馬・エイブルワンを勝利に導くレースをビデオで見ていた。鞭の使い方までそっくりに真似していたという。幼少期の多くを過ごしたのは、シャティン競馬場の関係者用住宅。同世代のルーク・フェラリス騎手、トム・プレブル騎手、ローナン・ファウンズ騎手らと一緒に遊び回っていた。
「最高の仲間でしたよ。同じ建物に住んでいましたから、一日中一緒に遊べました。子供にとっては最高の環境でした」
もっとも、遊び相手は人間だけではなかった。初めてのポニーの名前は『ミステリー』。だがその名の通り、一筋縄では手に負えなかった。
「騎乗を覚えるには最悪のポニーでした」と父ジェフは笑う。「ザックは必死でしたが、この小さなポニーは好き勝手に動きました。あまりに手に負えなくて途中で飛び降り、放してしまうこともありました。捕まえるのに30分もかかることがありましたよ」
ザックがまだ小学生の頃、51歳のジェフは脳卒中に倒れ、医師から「生き延びたのは奇跡だ」と告げられた。幼いザックは事態の深刻さを理解できなかったが、南アフリカで6度のリーディングを獲得し、通算4500勝以上を挙げていた父は再び騎乗できるかどうかに挑戦する決意を固めた。
本人いわく「水泳は大嫌い」だったが、リハビリに最も安全な方法は泳ぐことだった。プールの黒いラインに沿って何時間も泳ぎ続け、息継ぎのため横を向くことさえできず、シュノーケルを付けてひたすら前へ進んだ。
「できることは少なかったですが、シュノーケルがあれば泳げたんです。横を向けばバランスを崩すので無理でした。本当に大変でしたよ」とジェフは語る。
そんな父の執念と不屈の精神に、ザックは強い影響を受けた。やがて父が奇跡的なカムバックを果たしたとき、その思いは確信へと変わる。
「学校から帰ると、父が『今日はプールで10km泳いだ』って言うんです」とザックは振り返る。
「泳ぎなんて得意でもないのに。あの年齢でそこまで競馬のために努力できる人がどれだけいるでしょう。普通の人にはできません」
「僕にとって父は世界一の騎手でした。実績だけを見ればそうは言えないかもしれませんが、実績も十分積み上げていましたし、南アフリカでは神様のように扱われていました。今ならその理由がわかります。でも当時は、それが当たり前だと思っていたんです」
天才と先導役
競馬関係者の多くは知らないかもしれないが、ザックは本気になればサッカーとクリケット、2つのスポーツでも十分にキャリアを築ける才能を持っていた。
サッカーではミッドフィルダーとして非凡な力を発揮し、「疲れ知らずの機械みたいな選手でした」と父ジェフは振り返る。クイーンズランド州の選抜チームに何度も選ばれ、トップスカウトの前でプレーする欧州遠征のメンバーにも抜擢された。だが、その飛行機に乗ることはなかった。
「ただ、いつだって騎手になりたかったんです」とザックは肩をすくめる。
クリケットでも州代表ジュニアとして上位打線を任されるほどの腕前だった。しかし速球投手が成長し、小柄なザックめがけて容赦なくボールを投げ込むようになると、父はストップをかけた。
「もうやめた方がいいと言いました。ボールが頭の周りをかすめるのを何度も見ましたから。見てるこっちが怖かったんです。あまりに小柄でしたからね」

こうして、最終的に彼が選んだのは競馬の世界だった。ただし勉強も怠らず、母のニコラを喜ばせるために学業の成績も良好に保った。
そして初めて競走馬に跨がったとき、進むべき道は既に定まっていた。現在は引退した父ジェフがマネージャーとして騎乗を管理し、2人は毎日連絡を取り合う。レースが終わって20〜30分以内に電話がなければ、ジェフは「裁決室に呼ばれているのでは」と心配するほどだ。
もっとも、最近はその回数も減ってきている。
ジェフは息子の騎乗について、「とても野心的で、攻めの強さと冷静さのバランスを見つける必要がありました」と回想する。
「判断を急ぎすぎて失敗することもありましたが、少しずつ改善してきました。常に急ぎ足で進んできましたが、そのたびにハードルを上げ、短期間で多くを成し遂げました。だがまだ道のりは長いです」
シドニーの開催にはほぼ毎週、世界ランキングにも名前が載るような世界最高峰の騎手が参戦している。その中で、まだ22歳のロイドが、いずれマクドナルドと肩を並べる日が来るのは夢物語にすぎないのだろうか。
「もちろん、世界ナンバーワンになりたいと思っています」とロイドは断言する。
「22歳までは十分やれてきたと思いますが、まだまだ先は長いです」
ただし、父のように50代まで現役を続ける姿は期待しない方がいいだろう。それでもジェフとビードマン、この2人の存在は常に彼を支え続ける。
「彼には無限の可能性があります」と語るのはビードマンだ。
「素晴らしい青年で、若さという武器と天性の才能を持っています。その才能をどうコントロールし、どう導いていくかが重要です」
「私の恩師、セオ・グリーンさんがよく言っていました。『若い肩に年の功は載せられない』と。まさに今のロイドがその状態です。ただ、周囲の助言を受け入れることができれば、やがてその若い腕に “経験の知恵” が宿るはずです」
次回、マクドナルドに閉じ込められたとき、今度は “経験の知恵” で突破口を見つけ、裁決室に呼ばれることなく勝利を掴むことができるのか。それができる日はきっと、ロイドに訪れるはずだ。