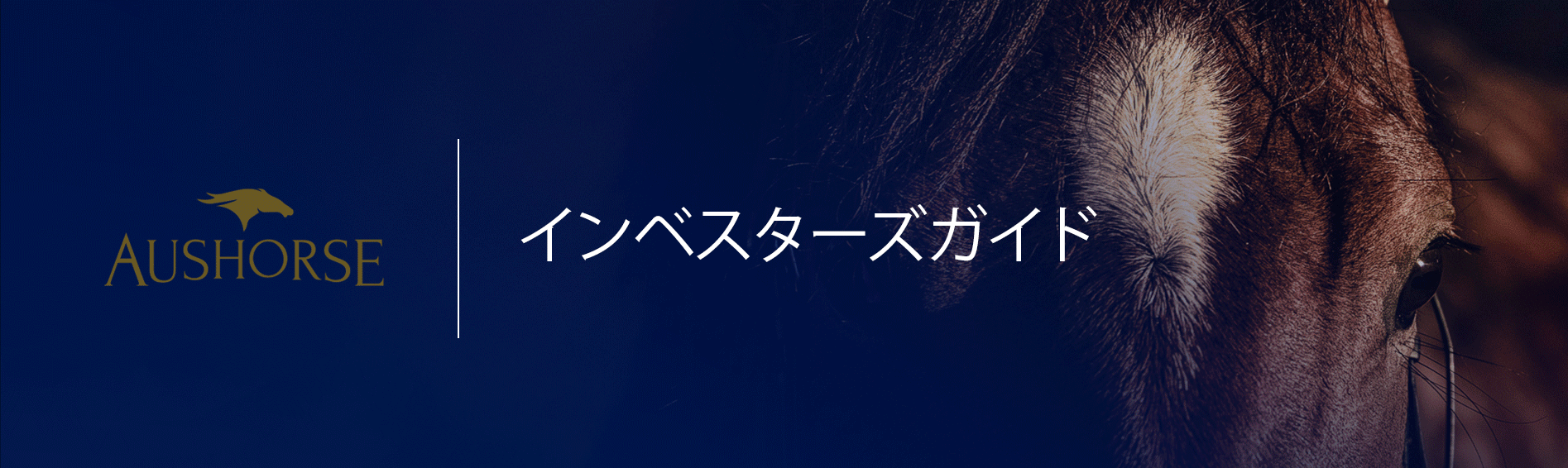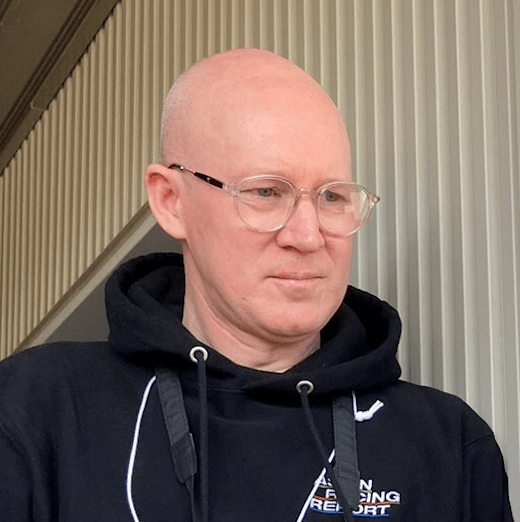池江泰寿調教師がオルフェーヴルについて語る時、彼からは畏敬の念が感じられた。それはある種の神話に対する驚嘆と言えるかもしれない。オルフェーヴルは、強靭な栗毛の馬体に秘められた、予測不能で謎めいた存在だった。
「オルフェーヴルは馬じゃないような動物でした。馬の中に人間が入ってるくらいというような、すごい知能が高い馬です。西遊記という中国のお話で馬がいるじゃないですか。人間が馬に化けてるような、まさにそんな感じです」と泰寿調教師は語った。
泰寿調教師が語る中で、2012年3月のG2・阪神大賞典でのオルフェーヴルの突飛な行動が思い浮かんだ。三冠達成と初の有馬記念制覇後、その年の初戦で、オルフェーヴルはレースすることを拒んだ。
池添謙一騎手の騎乗で残り800メートル地点まで先頭を走ったが、突然「もう十分だ」と言わんばかりに頭を曲げ、一気に後方へ。しかしその後、再び疾走を始め、外を大きく回って最終直線で先頭に迫るも、半馬身差で敗れた。
オルフェーヴルの最も有名な敗戦、2度目の凱旋門賞2着にも、その特異なメンタルが垣間見えた。クリストフ・スミヨン騎手を背に猛然と追い上げ、そして進路を逸れた―おそらくオルフェーヴルの意識が逸れたか、あるいは故意だったのかもしれないが―確実と思われた勝利が敗北に変わった瞬間だった。
「もちろん記憶力も高かったですし、人間に支配されることがすごく嫌いな性格でした」と泰寿調教師は語った。
彼は香港のシャティン競馬場で、愛馬のソウルラッシュが香港マイルで2着に入る2日前に、Idol Horseのインタビューに応じた。
「フォームがちょっと叩き付けるようなフォームでしたので、結構脚に疲れが溜まりやすかったですね。人間に支配されるのが嫌な馬だったので、担当者は力で押さえつけようっていう人じゃなくて、オルフェーヴルに友達のような感じで接してくれるような乗り手でした」と続けた。

ディープインパクトはオルフェーヴルとは異なる性格と馬質を持っていたが、やはり稀有な、実際には最も稀有な種類のチャンピオンだった。泰寿調教師は既に自身の調教師免許を取得していた時期に、父である泰郎氏がこのコンパクトな鹿毛の馬を担当することになった。
泰郎氏の言葉からも畏敬の念が伝わってきたが、この芝の伝説的存在について語る際、神話的な表現ではなく、日本最高の馬として世界で知られる馬への深い敬意が強調されていた。
「そんなに体型が大きい馬じゃなかったんでね、馬としてどっちかというと小型、小さい方でしたね。今思えばあんまり目立つ馬でもなかったし。それ以外は元気な子だな、っていうぐらいしか思えないですね」と泰郎氏は語る。淡々とした語りだが、シャティンの朝食ラウンジで愛馬の思い出を語る際、その老いた目は輝きを帯びていた。
「競走精神も良く、良い種牡馬として(良い産駒を)出しました。三冠馬ですけども、両方トップになっていった馬って少ないですが、こういう馬は僕も初めてですね。今まで見た中で、ディープはそういう面で優れた馬だったなって思います」
両馬は競馬の枠を超えて、その活躍期に注目を集めた。彼らは有馬記念の数々の印象的な歴史の中でも最も圧倒的な勝利を収めた馬として際立っており、またそれぞれ日本の三冠を達成した。
それだけでも素晴らしい偉業だが、各々の調教師が親子であることを考えると、さらに非凡な功績だ。

泰寿調教師は一瞬考え込んで、世界のどこかで親子がそれぞれ三冠馬を出したことはあるのかと尋ねた。歴史的に最も重要な二つの三冠を鑑みると、イギリスではそのような例はなく、アメリカについては微妙なところだった。
というのも、調教師のベン・ジョーンズと息子のジミー親子が1948年にサイテーションで米三冠を達成した際に、『ある意味では』それを成し遂げた。
ベン氏は既に1941年にワーラウェイで三冠を達成していた。ジミー氏はサイテーションのケンタッキーダービーでは父に史上最多勝に並ぶ4勝目を獲得させるため(後に6勝まで伸ばすことになる)免許を一旦父に移したが、実質的な調教師はジミー氏で、プリークネスステークスとベルモントステークスでは出馬表でも彼の名前に戻っていた。
83歳の泰郎氏と55歳の泰寿調教師は三冠達成で広く知られているが、彼らが競馬界での地位を築くきっかけとなったのは、ある中学校の体操教師だった。その教師は若き日の泰郎氏の機敏さと小柄な体格に目を付け、近くにあった京都競馬場の騎手を目指すことを勧めた。
それまで馬に乗ったことはなかったが、その助言を受け入れ、20年に渡って中堅騎手として活躍。これは、現在のようにJRA騎手が栗東と美浦の二つのトレーニングセンターに所属するのではなく、競馬場に所属していた時代のことだった。
彼のキャリアは世代を超えた繋がりを生み、今日まで続いている。特に日本最高の騎手である武豊との関係は注目に値する。武は14戦12勝という成績を残したディープインパクトの全レースで騎乗した。
「家庭環境は良く似ているんですよね。彼のお父さん(故・邦彦氏)も京都の騎手で、僕の方も騎手でして、泰寿は彼と同級生なんですよ。それで二人揃ってね、将来の騎手になるためにそういう施設に通って、乗馬やってたんです」と、泰郎氏は2人の間柄について振り返る。
「それで泰寿の方は体が大きくなったので、断念した。で、豊はそのまま騎手としてやっていく。で、(泰寿調教師は)『将来は俺が調教師になって武豊に乗ってもらうんだ!』ってね、そういう希望があったので、それが現実になった訳ですね」
泰寿調教師は、自分と武騎手は幼少期の頃から知り合いで、日本の競馬界のレジェンドとなった武騎手の人生の道筋に、自分もちょっとした役割を果たしたと述べた。
「僕が彼を乗馬クラブに誘ったんですね。それまでは野球チームに入ってて」とユーモアを交えて語った。
このような思い出話をする場所としてシャティンは完璧だった。ここは泰寿調教師が調教助手を務めていた2001年、泰郎氏が管理する社台レースホースのステイゴールドが武の騎乗で香港ヴァーズを制した場所だったからだ。
泰寿調教師はステイゴールドについて「なかなかG1を勝てない馬だったんですが、当時日本にはテイエムオペラオーという絶対的に強い馬がいて。このまま日本であの年の秋走り続けても、もうその年の年末で引退が決まってたので、このまま種馬になれなかったら可哀想で」と香港挑戦の経緯を語った。
「私がどうにかG1を勝たせるには、オペラオーがいる有馬記念ではなくて香港ヴァーズの方がチャンスが高いんじゃないかな、と進言したんです。父にそこを使いたいと。だからもう勝った瞬間は、もう言葉で表現できない嬉しさですね」と回想した。

泰寿調教師の成功したキャリア、864勝、そのうちG1勝利22回は、幼少期からの父の手本と指導に負うところが大きい。
「僕の仕事場で、ですね。競馬場の厩舎に、遊びかたがた連れて行った時に、3才か4才だと思いますね、馬乗りたいって言うので、乗せた覚えがあります。僕の仕事を見て、やりたいなっていう希望をもらって、それで調教師になったのでね、馬がものすごく好きな子だったので、良かったと思います」と泰郎氏は語った。
しかし泰寿調教師は、近年引退したイギリスの名伯楽サー・マイケル・スタウトと、もう一人のイギリス人調教師でアメリカに厩舎を置く、ニール・ドライスデールから学んだことも大きかったと認めている。彼は彼らの厩舎で経験を積み、観察し、耳を傾け、学び続けた。
「私の調教のベースにあるのはやっぱり彼(スタウト氏)のメソッドでありますし、だから競馬に向かう時とか、馬が状態の良くない時に、彼ならどういう決断をするんだろうなっていうのを想像しています」と泰寿調教師は説明した。
「ニール・ドライスデールさんは元々イギリス出身で、マイケル・スタウトさんとも親交が深くて、彼はアメリカ競馬でイギリス流調教を実践して成功した調教師さんです。僕は日本で調教師になりたかったので、イギリス流を日本に実践するにはどうしたらいいのかなということをいろいろニールから学びました」
「彼(スタウト氏)から直接言われた言葉が、『ファインド・ザ・ディテール』っていうものでした。馬の脚元とか、筋肉の状態だとか、顔の表情とか、馬の感情とか、そういう細かいところを感じ取りなさいという訳です。それを私の座右の銘にしています」
泰寿調教師は、これらの言葉がオルフェーヴルの特異な性格に対処する際に非常に役立ったことを認めた。
オルフェーヴルの存在自体が、父の調教師としての功績、特にシャティンでのラストランでステイゴールドがG1初勝利を果たし、ブリーダーズ・スタリオン・ステーション入りを確実にしたことと密接に結びついていた。その日の敗戦であれば、種牡馬入りではなく、乗馬としての余生となっていた可能性が高い。
ステイゴールドはオルフェーヴルの父である。それだけではない。オルフェーヴルの母、オリエンタルアートはメジロマックイーンの娘だった。メジロマックイーンは泰郎氏が調教し、武豊騎手が主戦騎手として騎乗。菊花賞、天皇賞(春)2勝、宝塚記念を制し、1991年の有馬記念では2着に入った名馬である。

有馬記念は偉大なレースだ。日本最大の競走であり、最高の競走でもある。ファン投票による出走馬選定、大観衆、重厚な歴史、印象的な優勝馬リスト、そしてその中心には琴線に触れるドラマがある。
現在は馬主となり、JRAの調教師を引退して久しい泰郎氏は、有馬記念を2度制している。最初は1987年のメジロデュレン、そして19年後にディープインパクトで勝利を収めた。
まだ全盛期にある泰寿調教師は、この競走を4度制している。2009年にドリームジャーニー、2011年と2013年にオルフェーヴル、そして2016年にサトノダイヤモンドが優勝を飾った。
2006年のディープインパクトの有馬記念は、一見努力を感じさせない驚異の運動能力を披露した。残り800メートルで後方から前進を開始し、最終コーナーで別次元のギアが入り、ライバルたちを華麗に突き放して、武騎手とともに楽々とゴールを通過。2着のポップロックに3馬身差をつけた。
それは、ロンシャンでの凱旋門賞3着(後に禁止薬物の痕跡が検出され失格)という落胆させる結果の後に訪れ、最後のレースで素晴らしい雪辱を果たした

2013年のオルフェーヴルも同様の物語だった。凱旋門賞でのトレヴへの敗戦はファンを落胆させ、今でもよく語られているが、その後の巻き返し、有馬記念での有終の美こそが、最も記憶に留めるべきものだ。それはまさに驚嘆すべき光景だった。
5歳馬は集団後方に位置取ったが、最終コーナーを回る時、池添騎手に手綱を抑えられながらもライバルたちを追い越していった。池添騎手はまるで単なる乗客のよう。直線に入ると既にオルフェーヴルが先頭に立ち、手綱を緩められながらも、ライバルたちに8馬身差をつけて勝利した。
7年前のディープインパクトと同様に、このチャンピオンもまた真の偉大な馬としてのレガシーを確かなものにした。
両馬のキャリアは、それぞれの調教師の評価を高め、池江泰郎、泰寿という名が、遠い将来まで記憶されることを確実にしたのだ。