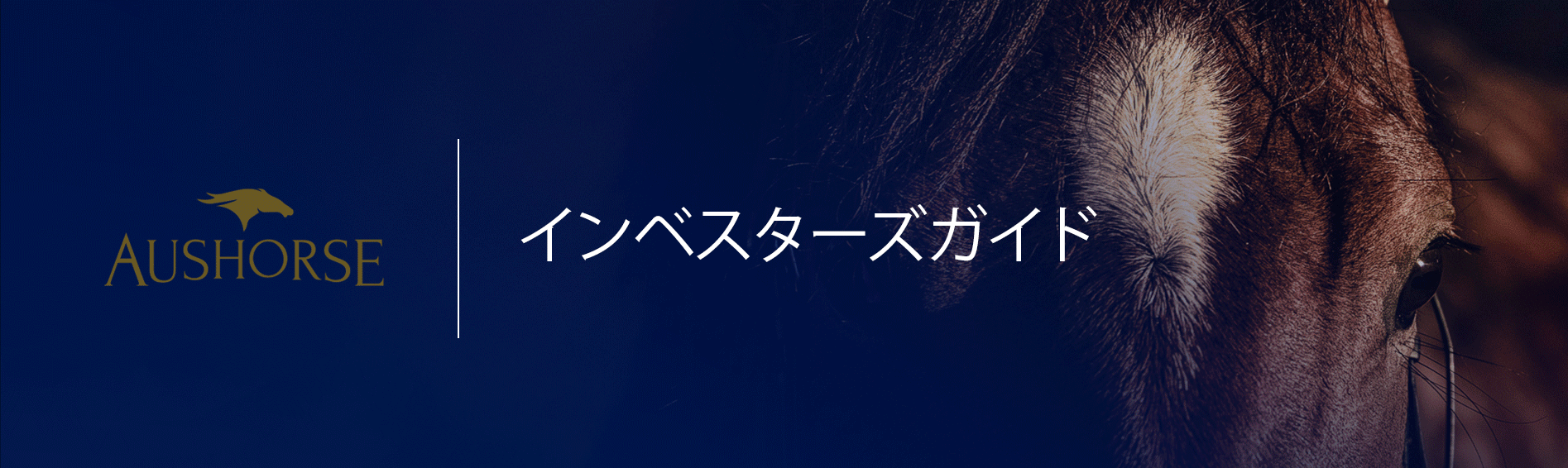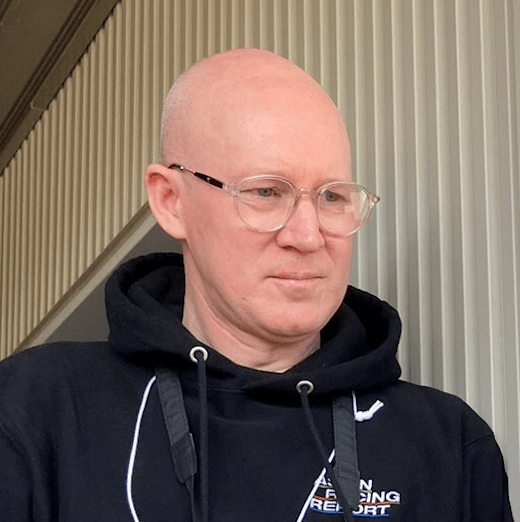ヨーク競馬場を視察した尾関知人調教師は、早速感銘を受けた様子だった。
彼は今まさに、歴史ある有名な競馬場を見学し終えたばかりだ。期待通りの設備であることを確認し、ドゥレッツァの輸送にゴーサインを出した。滞在先のニューマーケットから車で3時間かけ、北のナヴェスミアにある競馬場に輸送する。G1・インターナショナルステークスに出走するためだ。
「伝統の格式を感じるとともに、すごく美しい競馬場だなと思いました」
彼の言葉に間違いはない。ヨークでは古代ローマ人が競馬を行っていたと言い伝えられており、ナヴェスミアの地では300年以上も昔から近代競馬が行われている。
1851年、かの有名なザフライングダッチマンとヴォルティジュールのマッチレースが行われた競馬場でもある。ブリガディアジェラードがロベルトを相手に生涯唯一の敗北を喫した場であり、フランケルが伝説を残したコースでもある。
ヨーク競馬場のメルローズスタンド、1階ラウンジの席で尾関調教師は取材に応じてくれた。シャープにカットされた三角形のサンドイッチ、黄金色のフライドポテト、そして『豪華な』ヨークシャー料理に舌鼓を打っていた。外を見ると、灰色の雲が立ちこめて、スタンドはまだ静寂に包まれている。
インターナショナルステークスが開催される頃には、きっとヨーロッパ屈指の大レースを見るために訪れた何千人もの競馬ファンで賑わいを見せるだろう。

始まりはミスターシービー
クラシック制覇の経験もある調教師として、彼は競馬のあらゆる重要な出来事を経験してきた。彼が最初に競馬に出会ったのは約40年前、最初は一人のファンとして始まった。
「一番最初に行った競馬場は、中山競馬場ですね」
当時は中学一年生、まだ13歳のころに会社員の父に連れられ、競馬場に足を運んだ。父は大の競馬好きというわけではなく、G1レースがあれば見る程度だったという。
「千葉出身だったので、(中山競馬場は)近いので」
しかし、近くの競馬場のなんでもない一日に行ったわけではない。彼が初めて競馬と出会ったのは1984年の12月23日、日本を代表する年末のグランプリ、有馬記念にて3強対決が行われた日だった。熱狂の渦の真っ只中、彼は父親と共に間近で目撃した。
ミスターシービーとシンボリルドルフによる新旧の三冠馬対決、そして前月のジャパンカップを日本馬として初めて制したカツラギエース。この3頭が中山競馬場で激突したのだ。

尾関調教師は眼鏡越しにどこか遠くを見つめていたが、彼の視線はそこではない。心の中にある何か、彼の人生を変えたあの日の思い出を見つめていたのだろう。
「凄い盛り上がりで、競馬場自体も本当に凄い雰囲気でした」
「やっぱ見てても興奮するっていうか、凄いなぁと思って。凄く良いファーストインプレッションでしたね」
この取材はノーザンファーム国際部門の齋友祐氏がその場で通訳してくれたが、彼もまたその魔法のような記憶に引き込まれた一人だった。
「尾関調教師の話には興奮しました、その話は私も知らなかったです。凄いですね」
ミスターシービーは尾関調教師にとってヒーローだ。久しぶりの三冠馬誕生となった前年の活躍に心を奪われ、競馬の世界に引き込まれた。有馬記念でシンボリルドルフに敗れても、競馬への熱意が冷めることはなかった。

「小学校六年生の時に、ミスターシービーが三冠馬になって、久しぶりの三冠馬として凄いニュースになってて、それで競馬っていうのを知って。そこからはもう凄い知るごとに好きになって、ファンになりました」
懐かしい思い出を振り返る彼の顔には、自然と微笑みが浮かんでいた。
競馬の師匠
彼の出身は千葉県の八千代市、東京都心から東に20マイルほど離れた街だ。では、大好きな競馬とまだ繋がりがない10代の少年が、どのような道を辿ってJRAの調教師になったのか。ヨーロッパ屈指のビッグレースにクラシック勝ち馬を送り込むまでの道のりは、どのようなものだったのか?
「数年後、獣医になりました」
それが彼にとっての『入り口』だった。競馬の調教師になるという目標のため、獣医としての道を選んだ。尾関は夢に生きる競馬ファンだった。
岩手大学の獣医学科を卒業した後、1999年にJRA競馬学校の厩務員課程に入学した。卒業後の配属先となったのは、あの藤沢和雄厩舎。名マイラーのタイキシャトルがG1・ジャックルマロワ賞を制し、1週間前のシーキングザパールに次ぐ、日本馬2頭目の欧州G1制覇を達成した年の翌年だった。
藤沢和雄調教師は2005年、ゼンノロブロイでインターナショナルステークスに挑戦し、勝ち馬とクビ差の惜しい2着に入っている。

この時、藤沢厩舎で過ごしたのはわずか2ヶ月ほどだったが、この縁は後のキャリアに大きな影響を与えることになる。JRAの調教師試験に合格後、厩舎を開業するまでに1年間の研修期間が設けられる。尾関調教師が試験に合格した2008年、藤沢調教師はちょうど海外遠征を企画していた。
「ちょうどそのタイミングでカジノドライヴの海外遠征があったので、藤沢先生に勉強として行かせてほしいという話でお願いしました。最初はベルモントパークと、あとサンタアニタのブリーダーズカップの時もハリウッドパークへ、合わせて2回行きました。カジノドライヴはサンタアニタでアローワンスを勝って、ブリーダーズカップへ行きました。馬はハリウッドパークに滞在していました」
ベルモントパーク競馬場のG2・ピーターパンステークスの勝利と、G1・BCクラシックでの敗北、2008年のアメリカ遠征を振り返る。
「あのときは招待レースでもないレースへのチャレンジだったんですけども、その中でやってく大変さはあったと思います。そういうのも含めて、海外のトップレースへいつかは行きたいなという思いはずっとありました」
海外ではすでに実績を積み重ねている。G1・スプリンターズステークス連覇のレッドファルクスが2016年のG1・香港スプリントで惨敗した後も、彼は諦めなかった。3年後、グローリーヴェイズで香港に戻り、G1・香港ヴァーズを制覇。2021年にも、もう一度勝っている。
秋のロンシャンも経験した。キズナの帯同馬として厩舎のステラウインドをフランスに送り込んだ他、2023年にはG3勝ち馬のスルーセブンシーズがG1・凱旋門賞で4着に食い込んでいる。
「行く場所によって馬も違うし環境も違うし、その中で対応していくというところは勉強になります。その中で最低限の部分は共通する所もあって、その共通してる所を大事にして、臨機応変にやってくのは大事なのかなと思います」
「簡単に言うと、馬がハッピーでいられることと、それに加えて行った人もハッピーでなきゃいけないっていうところは大事です」


1999年に藤沢和雄厩舎で厩務員デビューを果たした後、藤原辰雄厩舎、そして同じく獣医師免許を持つ和田正道調教師の厩舎を渡り歩いた。その後、2002年から6年間、美浦の大久保洋吉厩舎で調教助手として働いた。
大久保調教師の経歴は、尾関調教師が歩んだ道とは大きく異なる。
騎手、そして調教師としても活躍した大久保末吉氏の長男として生まれ、騎手を目指していたが、体が大きくなりすぎたため断念。大学卒業後は建築士として働き、最終的に父の厩舎を手伝うという珍しい経歴を持っている。
「そういう個性もあって、ユニークな人です」
大久保調教師は今は引退し、競馬中継の解説者として人気を集めている。師匠との思い出について、尾関調教師は語ってくれた。
「トレーニングとかそういう色々な実務というか、そういう部分でも勉強になったとこはありました。例えば菊花賞に1勝馬を出したりとか、大久保先生は格上挑戦もよくあって。そういう時に会話の中で、『走ってない馬が勝つことはないからな』っていう話を聞いて、それは大久保先生の言葉で一番頭に残ってます」
大久保調教師の『走らない馬は勝てない』というアプローチは、かつてのクライヴ・ブリテン調教師を彷彿とさせる。彼が管理したテリモンは、単勝501倍の英ダービーで2着に入ると、その2年後には、まさにこのヨークで行われたインターナショナルSを単勝17倍の人気薄で制した。
ドゥレッツァを担当する矢原洋一調教助手も含めたチーム内では、テリモンの偉業が話題となっていた。
ドゥレッツァとの海外遠征
ヨーロッパを代表する3歳馬、シティオブトロイが出走するインターナショナルSではドゥレッツァもテリモンのようなオッズが予想されるが、尾関調教師はこの評価を全く気にしていない。彼は菊花賞を勝った直後から、海外遠征を見据えていた。G1・天皇賞春は不本意な結果に終わったものの、馬主のキャロットファームと相談した上で、ヨークを目標にすると決めた。
ドゥレッツァにとって最大の勝ち鞍は3000mの菊花賞だが、2050mへの距離短縮については心配していないという。ヨーク競馬場の平坦なコースは、ドゥレッツァのような先行馬にとって有利に働く可能性があり、短く刈り込まれた芝も日本馬向きだと見ている。

「秋のジャパンカップを目標にしたときに、ローテーションがスケジュールに組み込みやすかったのと、コースとかスタイルが合うかなってところが理由でした」
「距離に関しては、自分がこの馬がすごく走る馬だって感じたのは、香港ジョッキークラブトロフィーでした。去年の6月、東京の2000mの条件戦です。それまでもかなり良い馬だと思っていましたが、あそこを勝った時に少なくともグレードレース級の馬っていう感じを受けました。2000mへの距離短縮は決して突然の選択ではありません」
距離適性を判断する際に血統は重要な要素だが、それぞれの個性によって変わる部分でもあるため、一つのカテゴリーに固定することは避けたいとも考えている。気性、コントロール性、落ち着きなども鍵となると、経験を基に話してくれた。
「ブショウというマイル血統の馬が数年前にいました。新馬で2着と来て、段々勝てないうちに気が悪くなって、走らなくなってきた馬でした」
「ズブいから距離伸ばしてみようかと思って、2600m使ったら、ボロ負けで困ったなって思って。でも、集中力が持たないってことは逆に考えて、2600mの後に1000mの直線を使ったんです。それで未勝利戦を勝てて」
「たまたまの成功例ではあるんだけど、こんなこともあるから、先入観持たずにやってるかなって思います」
馬の多才さを信じ、馬の性格を理解しようとする姿勢が、厩舎の成功に繋がると彼は信じている。
「厩舎だけでなく、その前の牧場とか色々な人からたくさん教えてもらって、色々な引き出しを持たせてもらって。逆に何っていうのはないかもしれませんが、引き出しの多さが強みなのかなと思います」
52歳の尾関調教師は、個性的な名伯楽の下で多くを学び、若い頃にミスターシービーを見て憧れた競馬の世界で働いている。しかし、ここに辿り着くまでの原点を忘れることはない。
「まず、競馬ファンから始まって、こういう風に調教師になりました。競馬が好きだということです」