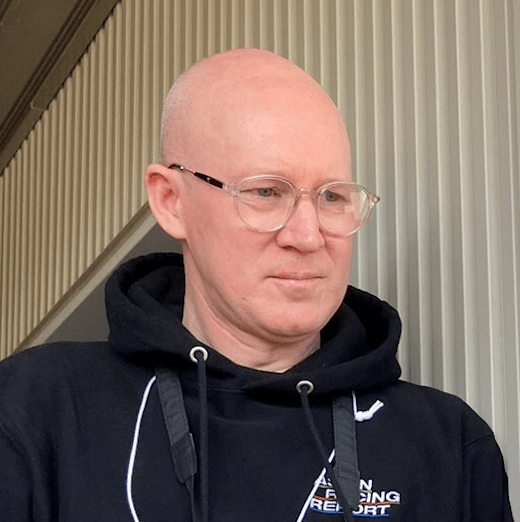先週末、京都競馬場のリバティアイランド像の前には、多くのファンが花や供え物を捧げていた。中には、彼女の華々しいキャリアと共にあったサンデーレーシングの黒、赤、黄色の勝負服に身を包んだ人々の姿もあった。香港での突然の死からわずか1週間後のことだった。
そうしたファンの光景は、彼女が2023年のG1・秋華賞を勝ち、牝馬三冠を達成した後に中内田充正調教師が語った「リバティアイランドは今やファンの皆さんのものです」という言葉を思い出させる。彼は当時、多くの人にとって彼女がいかに大切な存在かを意識し、その責任の重さを語っていた。
馬とファンとの絆は、秋華賞の4か月前、G1・優駿牝馬(オークス)のときに鮮明に表れた。鞍上の川田将雅騎手が、レース前に異例の呼びかけをして、リバティアイランドをはじめとした各馬が落ち着けるよう観客に静かにするよう求めたのだ。そして観衆はその願いに応えた。
「実は今のほうが、そのつながりを強く感じます」と中内田はIdol Horseの取材に語った。
「当時は彼女個人の、日々の様子に集中していたので、ほかのことを考える時間も余裕もありませんでした。キャリアを通じて、馬のことに集中してきました」
中内田にとって、リバティアイランドは単なる三冠牝馬ではなく、自信に満ち、唯一無二の個性を持った馬だった。
彼女の個性的な性格は、ノーザンファームの育成牧場を経て栗東トレセンに入厩したときから表れていた。その時点ですでに彼女の評判は高く、中内田厩舎は期待に満ちあふれていた。G1勝ち馬を母に持つこの快速牝馬は、本物かもしれないという期待感があった。
「早い段階からスピードと才能を見せてくれました。関係者全員が大きな期待を寄せていました」と中内田は振り返る。「2歳の頃は難しいところもあり、扱いやすい馬ではありませんでした。それでも、それは若さゆえのもので、悪いことだとは思いませんでした。彼女は彼女らしく振る舞っていただけです。元気で、何にでも興味を示していました」
「でも、走るとなると集中力がすごくて。自分からもっと速く、もっと前へと進もうとするんです。こちらが抑えなければいけないほどでした」

中内田がこのインタビューに応じたのは、リバティアイランドが香港のシャティン競馬場でG1・クイーンエリザベ2世カップに出走中に負傷し、安楽死となってから10日後のことだった。彼は、その瞬間やその後の影響について、自分の気持ちをうまく言葉にできないと語る。それは話したくないということではなく、愛馬を失ったことで生じた感情をまだ整理できていないという意味だった。
「今は厳しい時期です。厩舎だけでなく、リバティアイランドに関わってきた多くの人々にとってそうです」
「本当にたくさんの心温まるメッセージをいただき、皆さんから励ましの言葉をかけてもらいました。さまざまな形で支えられました」
さらに彼を支えたのは、この牝馬が歴史に名を刻んだ存在であるという事実だった。G1・桜花賞、優駿牝馬、秋華賞を制し、史上7頭目の牝馬三冠馬となった。さらに、G1・阪神ジュベナイルフィリーズも制しており、G1・ジャパンカップでは世界最強馬、イクイノックスを相手に2着に入った。
リバティアイランドの名声は日本国内にとどまらなかった。早々とその才能を開花させ、クラシック戦線を駆け抜けたその姿は多くの人々を魅了した。彼女のキャリアは卓越の連続であり、歓喜の高みと胸を締め付けるような挫折を含んでいた。そして、その物語は鮮烈な幕開けから始まった。
2022年7月30日、新潟競馬場。サンデーレーシングが所有する父・ドゥラメンテ、母・ヤンキーローズの牝馬。デビュー戦は1600mの新馬戦。鞍上の川田が全11戦で手綱を取ることになる、その第一歩だった。
「(川田)将雅は最初出会った日から彼女に強く惹かれ、愛情を注いできました」と中内田は語る。
「厩舎でも彼女は将雅にとても素直で、将雅も多くのビッグタイトルを手にしてきた騎手ですが、デビュー戦から引退まで全レースで騎乗したトップホースは彼女だけではないでしょうか。それだけリバティアイランドは将雅にとって特別な馬でした」
その日の新潟では驚くべきことが起きた。
「夏場で馬場は速く、しかも新潟は平坦です。持ち前の素質からすれば驚くことではないですが、それでも信じられない内容でした」と調教師は振り返る。
初陣の2歳牝馬は直線で外に持ち出されるとやや幼さを見せたが、川田がゴーサインを出すと一気に加速。ライバルたちを難なく交わし、3馬身差でゴール板を駆け抜けた。白いポンポンがたてがみに結ばれ、耳の間で揺れていた。ラスト600mは31.4秒。これは日本中央競馬会(JRA)の全距離、全世代で史上最速タイの記録だった。
そしてこのポンポンは、後に彼女の代名詞のような存在となった。桜の咲く春の桜花賞はピンク、初夏のオークスは赤、秋の秋華賞は黄色とオレンジ。色とりどりのポンポンは、担当厩務員の松崎圭介氏が結んでおり、このアイデアは松崎の妻から生まれたものだった。

驚異のデビュー勝ちの後、リバティアイランドはG3・アルテミスステークスに1.4倍の1番人気で出走。しかしラヴェルに首差の敗戦を喫した。だが、次走の阪神ジュベナイルフィリーズでは圧巻の走りを見せ、2馬身半差で勝利。圧倒的な内容に、陣営がクラシックだけでなく牡馬相手のダービー挑戦を検討するという噂まで流れた。
結局そのプランは実現しなかったが、鹿毛に流星と薄く途切れた白い筋の入った顔立ちの彼女は、阪神競馬場での桜花賞に1.6倍の1番人気で臨んだ。後方3番手、約8馬身後方から直線で大外に持ち出し、川田が合図を出すと強烈な伸び脚を見せた。残り200mではまだ厳しいかと思われたが、そこから突き抜けて勝利を手にした。
続くオークスでは、東京競馬場での晴れやかな午後に単勝1.4倍の圧倒的支持を受けた。直線で外から進出し、川田が軽く手綱を動かすと一気に加速。最後は6馬身差の圧勝だった。
「桜花賞の走りを見て、オークスは勝てるだろうと思っていましたが、まさかあそこまでの内容になるとは。完全に後続を置き去りにしていました」
4・5月のクラシック制覇後、リバティアイランドはノーザンファームしがらきで夏を過ごし、馬体重はその間に40~50kgほど増えた。10月15日、2000mの秋華賞で牝馬三冠に挑むことになる。
「あの日は特別な一日でした。3、4か月ぶりの実戦だったおかげか、随分とリラックスして臨めました。スイッチが入っていないのではと思えるほど、プレッシャーを感じずにレースを走ることができました」
京都競馬場の最終コーナーで力強く進出し、直線では川田の合図に応えて一気に加速。最後は余裕を持って1馬身差の勝利を収め、不朽の名声を手にした。
中内田は「観衆は彼女の走りに大興奮でしたし、皆があの内容を期待していたと思います」と語る。
「彼女を表現するなら『多才』という言葉がぴったりだと思います。マイルでも、2400mでも勝てる馬は多くありません。それを見事にやってのけました。桜花賞と優駿牝馬で見せたまったく異なるレーススタイルが、その証拠です」

リバティアイランドは、その卓越した能力と強い個性で多くの人々を魅了した。その名は、メジロラモーヌ、スティルインラブ、アパパネ、ジェンティルドンナ、アーモンドアイ、デアリングタクトといった歴代の三冠牝馬と並び、永遠に語り継がれることとなった。
ただ、桜花賞の時点でも秋華賞の時点でも、調教師は「まだ8割程度の仕上がりだった」と語っている。そして、その次に待ち受けていたのは、世界最強馬・イクイノックスに挑むジャパンカップ。まさに全力、過去最高のパフォーマンスが求められる舞台だった。
リバティアイランドは、当時4歳の最強牡馬イクイノックスに勝つことはできなかったが、堂々と食い下がり2着を確保。イクイノックスを除けば、他の一流馬たちを1馬身退ける素晴らしい走りだった。
中内田は「本当に素晴らしい走りを見せてくれました。敗れはしましたが、相手は世界一の馬です。あのパフォーマンスは本当に素晴らしかったです」と振り返る。
こうした活躍によって、翌4歳シーズンへの期待は高まった。だが、状況はそう簡単ではなかった。
2024年3月、ドバイ・メイダン競馬場で行われたG1・ドバイシーマクラシックでは、大外一気の末脚で3着に入り、復調を示したものの、その後、軽度と伝えられた前肢の靭帯炎が発覚。これにより春のローテーションは白紙となり、回復は夏から秋にずれ込んだ。
10月末、約1年ぶりの国内復帰戦となったG1・天皇賞・秋は、超一線級が集う中での出走に。だがレースでは仕上がり途上が響き、途中まで好位を追走したものの失速、13着の大敗に終わった。
しかし、そのレースが次への布石となった。12月にG1・香港カップ出走のためシャティン競馬場に遠征したリバティアイランドは、かつての輝きを取り戻しつつあった。直線では末脚を伸ばし、地元の名馬ロマンチックウォリアーを追い詰めて、2着。ラスト400mのタイムは22.46秒と、出走馬中最速だった。3着には2023年の日本ダービー馬、タスティエーラが入った。
1年後も、陣営は楽観的だった。2025年4月、G1・ドバイターフ(1800m)を目指しメイダン競馬場に向かったリバティアイランドは、調教ではリラックスした動きを見せていた。しかし、本番ではまだ実戦感覚が戻り切らず、8着に敗れた。
陣営は、この一戦を叩き台にして立て直しを図った。計画されたのは香港でのG1・クイーンエリザベス2世カップ。シャティン競馬場でも順調な追い切りを披露し、レースを迎えたが、直線で先頭に立ったタスティエーラを追って加速を始めた矢先、左前脚の靭帯を重度に損傷。無念にも、安楽死という決断が下された。
「人生に起きることは、全てに意味がある。私自身はこう捉えています」と中内田は語る。
「この経験から学び、未来に生かしていく。それこそが我々がやらなくてはいけないことです。他の馬たちのために、前を向いて最善を尽くさなければなりません」
「今は本当に厳しい時期ですが、やはり馬たちが私たちを支えてくれています」と彼は続ける。「競馬、そして人と馬との関係の不思議なところは、彼らがいつだって私たちを励まし、もう一度立ち上がらせてくれることです」